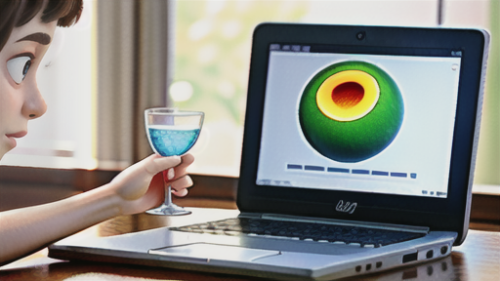ハードウエア
ハードウエア プラズマディスプレイ:鮮明な映像体験
画面を薄く作ることを可能にしたプラズマ画面の仕組みについて説明します。プラズマ画面は、薄いガラスの板を二枚使い、その間にネオンなどの気体を閉じ込めて作られています。この気体は普段は光っていませんが、電気を流すとプラズマと呼ばれる状態になり、目には見えない紫外線を出すようになります。この紫外線を利用して光を作り、画面に映し出すのがプラズマ画面の特徴です。二枚のガラス板には、紫外線が当たると光る塗料が塗られています。プラズマから出た紫外線がこの塗料に当たると、塗料が発光し、画面に色が映ります。この仕組みは、小さな蛍光灯を画面全体に敷き詰めたようなものです。一つ一つの蛍光灯のように、画面の小さな点が光ったり消えたりすることで、様々な映像を作り出しています。以前広く使われていたブラウン管テレビでは、電子銃と呼ばれる装置から電子ビームを蛍光面に当てて映像を表示していました。しかし、プラズマ画面では電子銃を使う必要がないため、画面を薄くすることが可能になりました。つまりプラズマ画面は、気体と紫外線、そして光る塗料を組み合わせることで、薄くて鮮やかな映像を実現しているのです。