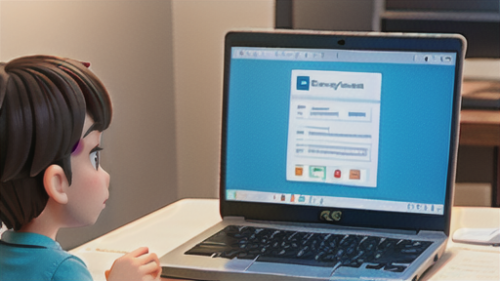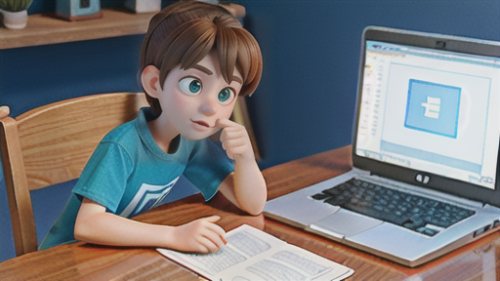開発
開発 改行文字LF:役割と注意点
文章を新しい行に送る、目には見えない特別な記号のことを、改行文字といいます。コンピュータの中で、文章の組み立てはこの記号によって決められています。普段私たちが文章を書き、新しい行を始めたいとき、何も考えずに使う「入る」と書かれたひらがな四文字のキー。このキーを押すと、新しい行が始まりますが、このキーの裏側で、実は改行文字がひそかに挿入されているのです。
改行文字は、文章を読みやすく、整理するだけでなく、様々な機械が文章を正しく扱うためにも、重要な役割を担っています。例えば、たくさんの情報を整理してしまっておく箱のようなものに文章をしまう場合、改行文字のある場所が、しまわれた情報の構造を決める手がかりとなることがあります。また、機械が文章を読み込んで、何らかの処理をする際にも、改行文字を区切りとして使うことで、それぞれの行を別々の情報として扱うことができます。
たとえば、歌の歌詞を考えてみましょう。それぞれの行が、改行文字によって区切られています。機械はこの区切りを利用して、一行ずつ歌詞を読み込み、画面に表示したり、カラオケのように歌に合わせて色を変えたりすることができるのです。もし、改行文字がなかったら、すべての歌詞がつながってしまい、どこで区切ればいいか分からなくなってしまいます。
このように、改行文字は目には見えない小さな記号ですが、文章の見た目や機械による処理において、なくてはならない重要な存在なのです。私たちが普段何気なく使っている「入る」と書かれたキーの裏側で、このような記号が活躍していることを、少し意識してみると、コンピュータの世界が少し違って見えてくるかもしれません。