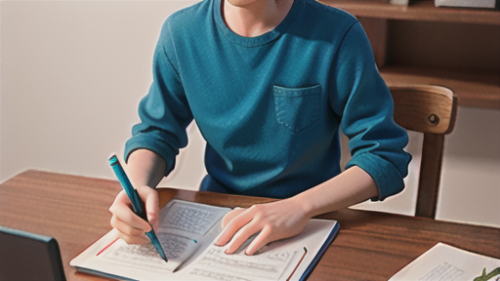ハードウエア
ハードウエア 磁気ディスク:データ保存の仕組み
磁気ディスクは、情報を磁気の力で保存する装置です。薄い円盤の形をしており、この円盤を「プラッタ」と呼びます。プラッタの表面は、磁気を帯びやすい物質でコーティングされています。このコーティングされた面に、小さな磁石のようなものが無数に並んでいると考えてください。これらの小さな磁石は、それぞれN極とS極を持ち、磁化の方向を変えることができます。
情報を記録する際には、電磁石を用いて、プラッタ表面の微小な領域を磁化します。磁化の方向がN極を上に向けた状態を「1」、S極を上に向けた状態を「0」と定義することで、デジタルデータを表します。プラッタは高速で回転し、読み書きヘッドと呼ばれる装置が、磁化された領域を読み書きします。読み書きヘッドは、プラッタ表面に非常に近づいていますが、接触はしていません。このため、データを何度も書き換えることが可能です。
磁気ディスクには、パソコンに内蔵されているハードディスクや、かつて広く使われていたフロッピーディスクなど、様々な種類があります。ハードディスクは、複数のプラッタを積み重ねて密閉したケースに収めたもので、大容量のデータを保存することができます。フロッピーディスクは、一枚のプラッタをプラスチックのケースに収めたもので、持ち運びに便利でした。近年では、小型で大容量の記録が可能な半導体メモリの発達により、ハードディスクやフロッピーディスクの使用頻度は減ってきていますが、依然として大容量のデータを安価に保存できるという利点から、多くのコンピュータシステムで利用されています。