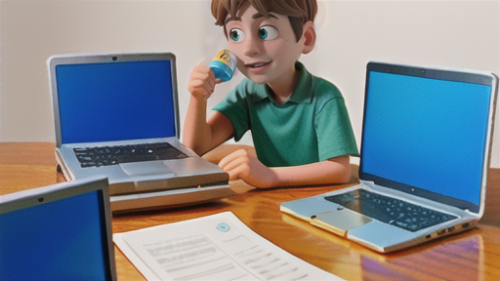 ハードウエア
ハードウエア パソコンを彩る周辺機器たち
計算機を使う上で欠かせないのが周辺機器です。周辺機器とは、計算機本体に繋げることで、計算機の働きをもっと良くしたり、操作を助けたりする機器のことです。計算機本体とは別に存在し、繋げることで初めてその役目を果たします。
私たちの周りには、色々な種類の周辺機器があります。例えば、文字を入力するためのキーボードや、画面上で指示を出すためのマウス、印刷をするための印刷機、画面に情報を映し出す画面表示機などです。これらは、計算機をより使いやすく、多くのことができるようにしてくれます。
計算機本体だけでは、情報を取り込んだり、外に出したりすることができません。周辺機器があるおかげで、私たちは計算機とやり取りをして、色々な作業を行うことができるのです。
例えば、キーボードとマウスは文字を入力したり、画面上の矢印を動かしたりといった基本的な操作を可能にします。画面表示機は、計算機が処理した情報を目に見える形で表示します。また、印刷機は計算機の中の情報を紙に印刷し、読み取り機は紙に書かれた情報を計算機で扱えるように変換することで、計算機との連携をより深めてくれます。
周辺機器には、情報を記録するための機器もあります。例えば、外付けの記録装置や記憶棒などです。これらは、計算機本体の記録容量を増やすことができ、たくさんの情報を保存しておくことができます。また、音を扱うための機器もあります。例えば、音を出すための発音機や、音を録音するための録音機などです。これらを使うことで、計算機で音楽を聴いたり、動画を見たり、音声通話をしたりすることができます。
このように、周辺機器は計算機をより便利に使うために無くてはならない存在です。色々な種類の周辺機器を理解し、うまく活用することで、計算機の可能性を最大限に引き出すことができるでしょう。








