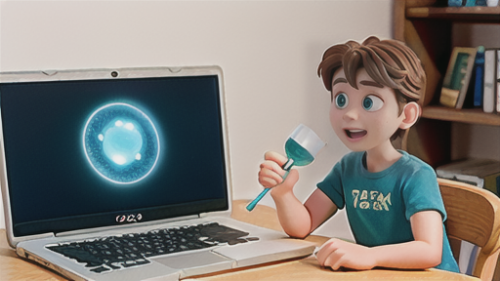ハードウエア
ハードウエア ドライブ:記憶装置への扉
計算機で書類や絵、写真といった情報を保管しておく装置を記憶装置と言います。この記憶装置には、色々な種類があります。例えば、硬い円盤に磁気を利用して情報を記録する磁気記憶装置や、光線を利用して情報を記録する光記憶装置、薄い磁気記録媒体をプラスチックの箱に収めた可搬型の記憶装置などがあります。これらの記憶装置は、それぞれ情報を記録する方法や持ち運びできるかどうかといった特徴が異なります。
これらの記憶装置に計算機から情報を書き込んだり、記憶装置から情報を読み出したりするために必要なのが駆動装置です。駆動装置は、記憶装置と計算機の間を取り持ち、情報をスムーズにやり取りするための橋渡し役を果たします。ちょうど、外国語を話す人と話す際に通訳が必要なように、計算機と記憶装置の間でも、情報を正しくやり取りするために駆動装置が必要なのです。
駆動装置にも、対応する記憶装置の種類に応じて様々な種類があります。磁気記憶装置に対応する駆動装置や、光記憶装置に対応する駆動装置、可搬型の記憶装置に対応する駆動装置などがあります。それぞれの駆動装置は、対応する記憶装置の特性に合わせて設計されており、適切な駆動装置を使うことで、記憶装置に保存された情報を効率よく読み書きすることが可能になります。もし、駆動装置がなければ、計算機は記憶装置にアクセスできず、情報を保存したり読み出したりすることができません。つまり、駆動装置は、計算機を有効に活用するために必要不可欠な存在と言えるでしょう。