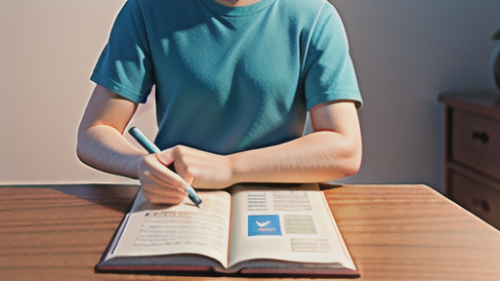画像
画像 色の表現:CMYKカラーモデルの仕組み
印刷物や出版物で目にする鮮やかな色彩は、一体どのように表現されているのでしょうか? コンピュータの画面表示とは異なる色の仕組みについて解説します。
私たちの身の回りにある印刷物、例えばチラシや雑誌、書籍などは、「色の掛け合わせ」という考え方で色を表現しています。絵の具を混ぜることを想像してみてください。青と赤を混ぜると紫になり、黄色と青を混ぜると緑になりますね。印刷もこれと同じように、特定の色を混ぜ合わせて多様な色を作り出しています。この色の組み合わせを「シアン・マゼンタ・イエロー・黒(CMYK)」といいます。
シアンは青緑のような色、マゼンタは赤紫のような色、イエローは黄色、そして黒は文字通り黒です。これらの四つの色を重ねて印刷することで、様々な色を表現します。例えば、シアンとマゼンタを重ねると青、イエローとマゼンタを重ねると赤になります。さらに黒を加えることで、色の濃淡や鮮やかさを調整しています。
パソコンやスマートフォンの画面表示は「赤・緑・青(RGB)」という光の三原色で表現されています。画面に光を直接当てることで色を作り出しているため、印刷物とは色の見え方が異なります。RGBは光を混ぜるほど明るくなりますが、CMYKはインクを重ねるほど暗くなります。これが、画面表示と印刷物で色の印象が異なる理由です。
このCMYKと呼ばれる色の仕組みを理解することは、デザイン制作や印刷物の仕上がりをより深く理解するために非常に重要です。例えば、パソコンで作成したデザインの色が、実際に印刷してみると少し違って見えることがあります。これは、RGBとCMYKの違いによるものです。色の仕組みを理解していれば、このような色の変化を予測し、より効果的なデザインを作成することが可能になります。