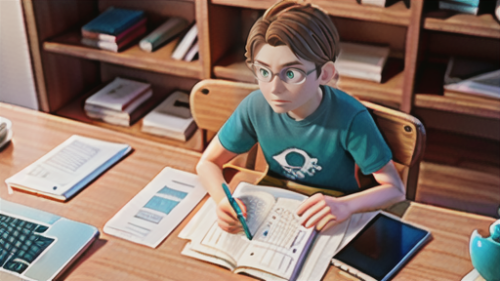規格
規格 情報処理を支える小さな巨人:シングルバイト文字
計算機の世界では、あらゆる情報を0と1の数字の組み合わせで表しています。この0か1の最小単位を「ビット」といいます。電気が通っているかいないか、磁気がS極かN極か、といった二者択一の情報を表すのに最適です。ちょうど、電灯のスイッチのオンとオフのように、二つの状態を表現できます。そして、この小さな「ビット」が8つ集まって、ひとまとまりになります。この8ビットの塊を「バイト」と呼びます。
この「バイト」は、計算機が情報を扱う際の基本的な単位です。1バイトあれば、2の8乗、つまり256通りのパターンを表現できます。この256通りのパターンで、様々な記号や文字を割り当てて表現しているのです。例えば、アルファベットのAやB、数字の1や2、記号の!や?など、たくさんの文字や記号をこの1バイトで表すことができます。ひらがなやカタカナ、漢字といった日本語の文字は、1バイトでは表現しきれないものも多く、2バイトやそれ以上が必要になります。
1バイトで表現できる文字のことを「1バイト文字」または「半角文字」といいます。半角文字は、主にアルファベットや数字、記号などです。一方、ひらがなやカタカナ、漢字といった日本語の文字は、多くの場合「全角文字」と呼ばれ、2バイト以上を使って表現されます。画面上で文字を表示する際、半角文字は全角文字の半分の幅で表示されるため、この呼び名がついています。わずか8個の0と1の組み合わせで、これほど多くの情報を表現できることは驚くべきことです。この0と1の組み合わせこそが、現代の情報社会を支える礎となっているのです。