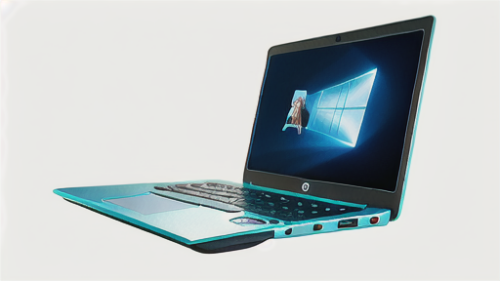 ハードウエア
ハードウエア システムメモリ:コンピュータの短期記憶
計算機の中核部品の一つであるシステム記憶装置は、処理途中の情報や手順を一時的に保管する場所です。これは、ちょうど仕事をする机のような役割を果たします。机の面積が広ければ、たくさんの書類や道具を広げて作業できます。同様に、システム記憶装置の容量が大きければ、たくさんの手順を同時に進めたり、大きな資料を扱ったりすることが楽になります。
システム記憶装置は、計算機の心臓部である中央処理装置が直接情報をやり取りする場所です。中央処理装置は、システム記憶装置に保管された情報や手順を読み込んで処理を行います。このため、システム記憶装置の速度は計算機の全体の処理速度に大きな影響を与えます。システム記憶装置が高速であれば、中央処理装置は必要な情報を速やかに読み込むことができ、処理速度が向上します。逆に、システム記憶装置が低速であれば、中央処理装置は情報を待つ時間が長くなり、処理速度が低下します。
システム記憶装置は、電源を切ると保管されていた情報が消えてしまう性質を持っています。これは、揮発性記憶装置と呼ばれる特性です。このため、長期間の情報の保管には適していません。長期間の情報の保管には、固体記憶装置や磁気記憶装置といった、電源を切っても情報が消えない不揮発性記憶装置が用いられます。システム記憶装置の役割は、処理速度の向上にあり、中央処理装置がすぐに使える場所に必要な情報を置くことで、計算機全体の性能を大きく左右します。システム記憶装置は、計算機の性能を左右する重要な部品であり、その容量や速度は、計算機の処理能力に直結します。適切な容量のシステム記憶装置を選ぶことで、快適な作業環境を実現できます。





