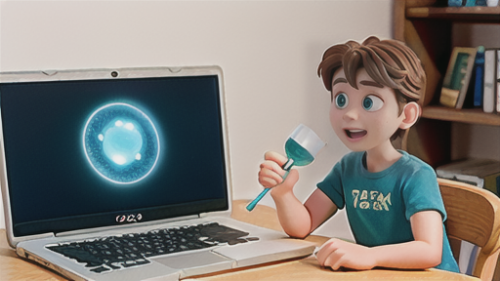ハードウエア
ハードウエア 懐かしのPS/2ポート:今、なぜ重要なのか?
1987年、技術革新の波が世界を覆う中、国際事務機械株式会社は画期的な個人向け計算機「ピーエスツー」を発表しました。この計算機は、それまでの常識を覆す様々な新しい機能を搭載し、現代の計算機の基礎を築いた重要な存在と言えるでしょう。その中でも特に注目すべきは、文字入力装置と位置指示装置を接続するための新たな規格「ピーエスツー接続口」の登場です。円形の形状をしたこの小さな接続口は、瞬く間に業界の標準となり、長年にわたって個人向け計算機周辺装置の接続方法を定める存在となりました。
それまでの接続口は大きく、場所を取るものが主流でした。加えて、装置ごとに形状が異なり、利用者は接続に戸惑うことも少なくありませんでした。ピーエスツー接続口は小型で統一された規格であったため、接続の簡素化に大きく貢献しました。また、複数台の周辺装置を同時に接続できるようになり、利用者の利便性も向上しました。この接続口は、色分けによって識別できるようにも設計されており、緑色は位置指示装置、紫色は文字入力装置に割り当てられました。この工夫により、利用者は見た目で接続先を判断できるようになったのです。
ピーエスツー接続口は、後に登場する「汎用直列バス」などの新しい接続方式に取って代わられるまで、長期間にわたって広く利用されました。現代の計算機では、その姿を見ることは少なくなりましたが、ピーエスツー接続口は個人向け計算機の歴史を語る上で欠かせない要素の一つと言えるでしょう。その小さな接続口は、技術の進歩を象徴する存在として、今もなお私たちの記憶に刻まれています。