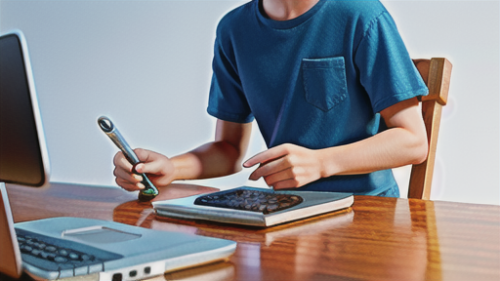WEBサービス
WEBサービス サイトマップで迷子の回避
初めて訪れた場所に、分かりやすい案内図があると安心しますよね?インターネット上の場所、つまりホームページでも同じです。たくさんの情報が掲載されているホームページでは、目的の情報を見つけるのが難しい場合があります。まるで、広い建物の中で迷子になったような気持ちになるかもしれません。そんな時に役立つのが「案内図」、ホームページでは「場所図」と呼ばれるものです。
場所図は、ホームページ全体の構成を分かりやすく示した図です。建物の各階ごとの案内図と同じように、ホームページにある様々な情報がどのように整理され、どこに配置されているのかが一目で分かります。場所図には、ホームページにある全ての部屋、つまりページへの入り口が示されています。例えば、「お知らせ」や「商品のご案内」、「会社概要」といった情報が、それぞれどこに掲載されているかがすぐに分かります。まるで、建物の案内図で「お手洗い」や「出口」を探すのと同じです。
場所図の見方は簡単です。図の中の文字や絵を押し示すことで、その情報が掲載されているページに直接移動できます。例えば、「商品のご案内」という文字を押すと、商品の一覧が表示されているページに移動します。また、場所図はホームページのどのページからでも見られるように、分かりやすい場所に設置されていることが多いです。通常、ホームページの上部や下部、あるいはメニューの中にあります。「場所図」と書かれた文字や案内図の記号を見つけて押してみましょう。
場所図を使うことで、ホームページの中を迷わずに目的の情報にたどり着くことができます。まるで、案内図を見ながらスムーズに目的地まで歩けるのと同じです。ぜひ、ホームページを訪れた際には、場所図を活用して、快適に情報収集をしてみてください。