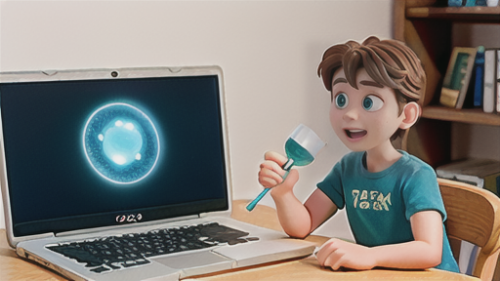ハードウエア
ハードウエア 懐かしの記憶装置:FDドライブ
計算機で扱う情報は、すべて数字の列で表され、その情報を保管する場所が記憶装置です。記憶装置には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。情報を一時的に保管する主記憶装置と、情報を長期的に保管する補助記憶装置に大きく分けられます。主記憶装置は、計算機が動作している間だけ情報を保持し、電源を切ると情報は消えてしまいます。補助記憶装置は、電源を切っても情報を保持できます。
かつて、書類作成や情報の持ち運びによく使われていたのが、フロッピーディスク装置です。薄い円盤状の記録媒体に磁気を使って情報を記録する仕組みで、手軽に持ち運べるのが特徴でした。フロッピーディスクは、大きさや容量によって様々な種類があり、8インチ、5.25インチ、3.5インチといったサイズが普及しました。特に、3.5インチのフロッピーディスクは、堅牢なプラスチックケースに収められており、広く使われました。
しかし、フロッピーディスクは容量が少なく、読み書きの速度も遅いという欠点がありました。技術の進歩とともに、より大容量で高速な記憶装置が登場し、フロッピーディスクは次第に使われなくなっていきました。現在では、小型で軽量、大容量のUSB記憶装置や、ネットワークを通じて情報を保管するクラウド記憶装置などが主流となっています。これらの記憶装置は、フロッピーディスクに比べてはるかに多くの情報を保管でき、読み書きの速度も格段に速くなっています。
フロッピーディスクは、今ではほとんど見かけなくなりましたが、かつて計算機を使う上で欠かせない存在でした。フロッピーディスクの歴史や仕組みを学ぶことで、記憶装置の進化や計算機技術の発展を理解する上で貴重な手がかりとなります。