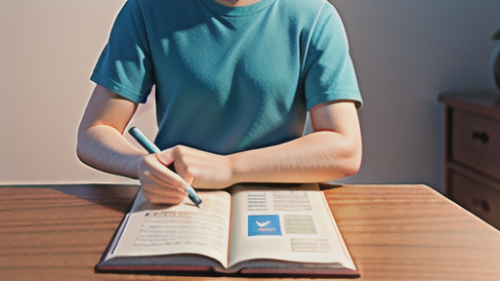 画像
画像 印刷に適した色の表現:CMYKカラースペース
私たちは日々、様々な印刷物を見かけます。街中で配られるちらし、本屋に並ぶ雑誌や書籍など、これらは皆「色の三原色」とは異なる仕組みで色を作り出しています。印刷物に使われているのは「シアン(青緑色)」「マゼンタ(赤紫色)」「イエロー(黄色)」「黒」の四つの色で、この四色を混ぜ合わせて様々な色を表現しています。この色の表現方法を「シエムワイケー」と呼びます。
色の三原色は、絵の具のように色を混ぜるほど色が濃くなり、最終的には黒に近づきます。しかし、印刷物はこれとは反対に、色を重ねるほど光を吸収して暗くなる性質を持っています。これを「減法混色」と言います。白い紙に光が当たると、その光は様々な色を含んでいます。シアンのインクは赤い光を吸収し、マゼンタは緑の光を吸収、イエローは青い光を吸収します。つまり、これらのインクは白い光から特定の色を取り除くことで、私たちにはそのインクの色として見えているのです。例えば、シアンとマゼンタのインクが重なると、赤と緑の光が吸収され、残った青い光が私たちの目に届き、青色に見えます。
黒は理論上、シアン、マゼンタ、イエローの三色を混ぜれば作ることができます。しかし、実際には綺麗な黒色を作るのが難しいため、黒インクは単独で使用されます。また、黒インクを使うことで、インクの使用量を減らし、印刷にかかる費用を抑える効果もあります。




