ものづくりを革新するコンピューター支援設計製造

ITを学びたい
先生、「コンピューター支援設計製造システム」って、何ですか?なんだか難しそうでよくわからないです。

IT専門家
簡単に言うと、コンピューターを使って設計と製造を支援するシステムのことだよ。設計の段階では、コンピューターで図面を描いたり、3次元モデルを作ったりできる。製造の段階では、コンピューターで工作機械を制御して、部品を作ったりできるんだ。

ITを学びたい
へえー。つまり、コンピューターで設計図を描いて、その設計図通りにコンピューターが部品を作れるってことですか?

IT専門家
その通り!コンピューター支援設計製造システムのおかげで、設計から製造までがスムーズになり、時間もコストも削減できるんだよ。
コンピューター支援設計製造システムとは。
「情報技術」に関する言葉である「コンピューターを使って設計や製造を助ける仕組み」(つまり「キャドカム」と呼ばれるもの)について
はじめに

ものづくりを取り巻く環境は、近年、著しい変化を見せています。より早く、より精密に、そしてより複雑な製品が求められるようになり、従来の手作業による設計や製造では限界が見え始めています。そうした中で、ものづくりの世界に革新をもたらしたのが、電算機援用設計製造組織、いわゆるキャドキャムです。
キャドキャムとは、設計から製造までの工程を電算機上で一貫して行う組織のことです。製品の形状や寸法を定める設計段階では、設計者は画面上で図面を作成し、修正することができます。立体的な映像で確認しながら作業を進めることができるため、設計の正確性と効率が格段に向上します。また、電算機上で設計データを管理することで、データの共有や再利用も容易になり、設計変更にも柔軟に対応できます。
製造段階においても、キャドキャムは大きな力を発揮します。設計データに基づいて工作機械を制御することで、複雑な形状の部品でも高精度に加工できます。人の手では不可能な微細な加工や、大量生産にも対応できるため、製造の効率化と品質向上に大きく貢献します。さらに、電算機上で加工工程を模擬することで、事前に問題点を発見し修正することも可能です。これにより、手戻りや不良品の発生を抑え、コスト削減にも繋がります。
キャドキャムは、もはや現代のものづくりになくてはならない存在です。自動車や航空機、家電製品など、私たちの身の周りの様々な製品の製造に活用されており、ものづくり産業の競争力強化に欠かせない技術となっています。今後、ますます高度化・複雑化するであろうものづくりのニーズに応えるため、キャドキャムは進化を続けていくことでしょう。
| 工程 | キャドキャムの役割 | 効果 |
|---|---|---|
| 設計 | 画面上で図面作成・修正、立体映像での確認 | 設計の正確性と効率向上、データ共有・再利用、設計変更への柔軟な対応 |
| 製造 | 設計データに基づいた工作機械制御、加工工程の模擬 | 複雑な形状の部品を高精度に加工、微細加工や大量生産対応、製造効率化と品質向上、問題点の事前発見と修正、コスト削減 |
設計と製造を繋ぐ

設計と製造の連携は、製品づくりの流れにおいて昔も今も変わらず重要な課題です。かつては、設計図を人が手で描き、それを基に製造現場で作業を進めていました。しかし、このやり方には、図面を読み解く際の解釈の違いや、人が作業を行う際にどうしても起こってしまうミスといった問題点が潜んでいました。人が介在する作業が多いため、どうしても間違いが生じやすく、その修正にも時間と費用がかかっていました。
たとえば、設計の修正が必要になった場合、設計者は修正した図面を再び作成し、製造現場に伝えなければなりません。製造現場では、その変更内容を理解し、作業手順や工具などを調整する必要がありました。このようなやり取りが、製品完成までの時間を長引かせ、費用を押し上げていたのです。
そこで登場したのが、設計と製造をコンピューター上で繋ぐ技術です。設計の段階でコンピューターを使って製品の設計データを作り、そのデータをそのまま製造機械に送ることで、従来の方法にあった問題点を解決することができます。図面の解釈の違いや人為的なミスを無くし、設計から製造までの一連の流れをスムーズにすることが可能になります。
この技術によって、設計変更も容易になります。設計データ上で修正を行い、それを即座に製造機械に反映させることができるため、試作品を作るのにかかる時間や費用を大幅に減らすことができます。また、修正作業も迅速に行えるため、製品開発のスピードアップとコスト削減に大きく貢献します。
設計と製造をコンピューター上で繋ぐ技術は、ものづくりのあり方を変えつつあります。より精度の高い製品を、より速く、より安く作り出すことを可能にし、製造業全体の競争力向上に役立っています。
| 従来の方法 | コンピューターを使った方法 |
|---|---|
| 人が手で設計図を作成 | コンピューターで設計データを作成 |
| 図面の解釈の違いや人為的ミスが発生 | 図面の解釈の違いや人為的ミスを排除 |
| 設計変更に時間がかかり、費用も高額 | 設計変更が容易で、迅速かつ低コスト |
| 製品完成までの時間と費用が増加 | 製品完成までの時間と費用を削減 |
| 試作品作成に時間と費用がかかる | 試作品作成の時間と費用を大幅に削減 |
3次元モデルで視覚化

設計の現場では、コンピューター支援設計、いわゆるキャドが広く使われています。この技術は、製品を立体的な模型として画面上に作り出すことを可能にします。まるで実物が目の前にあるかのように、あらゆる角度から眺めることができ、完成形を事前に把握できるため、外観デザインの検討がしやすくなります。機能面についても、部品同士の干渉や動きの確認など、様々な検証を行うことができます。例えば、歯車が噛み合う様子や、ロボットアームの可動範囲などを3次元模型上でシミュレーションすることで、設計段階で問題点を発見し、修正することが可能になります。
従来の平面図面では、複雑な形状を正確に伝えることが難しく、特に奥行きや曲面を持つ部品の設計では、製作者の経験や解釈に頼る部分が多くありました。しかし、3次元模型を使うことで、設計者の意図を明確に伝えられます。細部に至るまでコンピューター上で再現できるため、製造現場との意思疎通もスムーズになり、誤解や手戻りを減らすことができます。また、3次元模型は、様々な角度から断面図を作成することも容易です。内部構造の確認や部品同士の接続部分の設計など、平面図面では表現しきれなかった情報を分かりやすく伝えることができます。このように、3次元模型を活用することで、設計から製造までの全工程において、品質の向上と効率化が期待できます。 特に、複雑な形状の製品開発においては、3次元模型は欠かせない技術となっています。
| メリット | 従来の問題点 | 具体的な効果 |
|---|---|---|
| 外観デザインの検討が容易 あらゆる角度から完成形を事前に把握可能 |
平面図面では複雑な形状を正確に伝えることが難しい 製作者の経験や解釈に頼る部分が多い |
設計者の意図を明確に伝えられる 製造現場との意思疎通がスムーズになる |
| 機能面の検証が可能 部品同士の干渉や動きの確認、シミュレーションができる |
設計段階で問題点を発見し、修正できる 誤解や手戻りを減らせる |
|
| 様々な角度から断面図を作成容易 内部構造の確認や部品同士の接続部分の設計 平面図面では表現しきれない情報を分かりやすく伝えられる |
品質の向上と効率化 特に、複雑な形状の製品開発においては欠かせない技術 |
自動化による効率向上
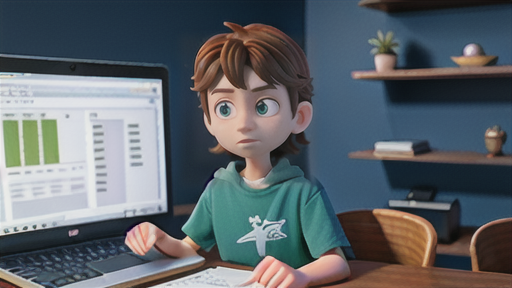
自動化を取り入れることで、ものづくりの現場は大きく変わります。人の手を介さなくても、あらかじめ組み込まれた手順に従って機械が自動で動くことで、様々な恩恵が生まれます。
まず、生産性が飛躍的に向上します。従来、人の手で行っていた作業を機械が肩代わりすることで、作業時間は大幅に短縮されます。例えば、金属の塊から複雑な部品を作るといった作業を想像してみてください。人が一つ一つ丁寧に削り出していたのでは、多くの時間と労力がかかります。しかし、工作機械にあらかじめ作業手順を教え込んでおけば、休むことなく、正確に作業を進めてくれます。これにより、同じ時間でより多くの製品を作ることが可能になります。
品質の均一化も大きなメリットです。人の手による作業では、どうしても仕上がりにばらつきが生じてしまいます。熟練した職人であれば高い精度で作業できますが、経験の浅い作業者では同じ品質を保つのが難しい場合があります。しかし、機械による自動化であれば、誰が操作しても常に同じ手順で作業が行われるため、どの製品も同じ品質を維持できます。まるで熟練の職人が作ったかのような、精巧な製品を誰でも簡単に作れるようになるのです。
複雑な形状の加工も容易になります。人の手では難しい、複雑で精緻な加工も、機械なら正確にこなせます。あらかじめ設計図通りの手順を機械に教え込むことで、ミクロン単位の誤差も許されない精密な部品も作ることができます。
さらに、作業者の負担軽減と安全性の向上も見逃せません。重労働や危険な作業を機械が代行することで、作業者の肉体的、精神的な負担を軽減し、安全な作業環境を実現できます。また、夜間や休日も機械が稼働し続けることで、生産効率をさらに高めることも可能です。このように、自動化はものづくりの現場における様々な課題を解決し、より良い未来へと繋がる大切な技術と言えるでしょう。
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 生産性の向上 | 機械による自動化で作業時間が短縮され、生産量が増加。 |
| 品質の均一化 | 誰が操作しても同じ手順で作業が行われるため、均一な品質の製品を製造可能。 |
| 複雑な形状の加工 | 機械による精密な加工で、複雑な形状の製品も容易に製造可能。 |
| 作業者の負担軽減と安全性の向上 | 重労働や危険な作業を機械が代行し、作業者の負担を軽減し、安全性を向上。 |
様々な分野での活用

設計支援用ソフト(キャドキャム)は、機械部品作りだけでなく、建物、乗り物、宇宙開発、医療など、幅広い分野で役立っています。建物の分野では、設計図作りや構造計算に活用されています。建物の形や配置を決めたり、地震や風に対する強さを調べたりする際に、コンピュータ上で緻密な作業ができます。乗り物の分野、特に自動車や飛行機、宇宙船などの設計や製造にも、キャドキャムは欠かせません。複雑な部品の形を正確に設計し、それらを組み合わせることで、より安全で性能の良い乗り物を作り出すことができます。宇宙開発では、ロケットや人工衛星の設計に利用され、宇宙探査の進歩に貢献しています。
医療分野では、人工関節や埋め込み器具の設計・製造にキャドキャムが役立っています。患者一人ひとりの体に合わせて、オーダーメイドの医療機器を作ることが可能になり、治療の精度向上に繋がっています。このように、キャドキャムは様々な製品の開発や製造に欠かせない技術となっています。あらゆる分野でのものづくりを支える重要な役割を担っていると言えるでしょう。
これからのキャドキャムは、さらに進化していくと期待されています。例えば、人工知能(AI)と組み合わせることで、設計作業を自動化したり、より良い設計案を提案したりすることが可能になるでしょう。また、立体造形機との連携によって、従来の方法では難しかった複雑な形の製品を簡単に作れるようになる可能性も秘めています。キャドキャム技術の進歩は、ものづくりの未来を大きく変える力を持っていると言えるでしょう。
| 分野 | キャドキャムの活用例 |
|---|---|
| 建物 | 設計図作成、構造計算(地震、風に対する強度の解析)、建物の形や配置の決定 |
| 乗り物(自動車、飛行機、宇宙船など) | 複雑な部品の設計、部品の組み合わせ、安全性と性能の向上 |
| 宇宙開発 | ロケット、人工衛星の設計 |
| 医療 | 人工関節、埋め込み器具の設計・製造(患者一人ひとりに合わせたオーダーメイド医療機器) |
| 今後の展望 | 期待される効果 |
|---|---|
| AIとの連携 | 設計作業の自動化、設計案の提案 |
| 立体造形機との連携 | 複雑な形の製品製造 |
今後の展望

設計・製造支援の電子情報処理技術を取り巻く状況は、常に変化し続けています。近年、人工知能や機械学習を取り入れた設計支援技術、立体造形機などの積層造形技術との組み合わせ、仮想現実や拡張現実を活用した設計・製造工程など、様々な新しい技術が登場しています。これらの技術の進歩は、設計・製造支援の電子情報処理技術の可能性を大きく広げ、ものづくりの未来を大きく変える力を持っています。
例えば、人工知能は、過去の設計情報を学習することで、新しい設計案を自動的に生成したり、最適な設計パラメータを提案したりすることが可能になります。また、機械学習は、大量の製造データから不良品発生の要因を分析し、製造工程の改善に役立てることができます。立体造形機は、従来の製造方法では難しかった複雑な形状の部品を容易に製造することを可能にし、設計の自由度を飛躍的に高めます。仮想現実や拡張現実は、設計者や製造技術者が仮想空間で設計モデルを3次元的に確認したり、製造工程をシミュレーションしたりすることを可能にし、設計・製造の効率化に大きく貢献します。
これらの技術革新により、より高度な設計、より効率的な製造、そしてより革新的な製品が生まれることが期待されます。設計・製造支援の電子情報処理技術は、これらの技術を取り込みながら、今後も進化を続けていくでしょう。それと同時に、これらの新しい技術を使いこなせる人材の育成も、ものづくりの未来にとって非常に重要な課題となります。教育機関や企業は、積極的に人材育成に取り組み、技術革新の波に乗り遅れないように努力していく必要があるでしょう。
| 技術革新 | 設計・製造支援への影響 | 期待される成果 |
|---|---|---|
| 人工知能・機械学習の活用 | – 新しい設計案の自動生成 – 最適な設計パラメータの提案 – 不良品発生要因の分析と製造工程改善 |
より高度な設計 |
| 積層造形技術(立体造形機) | – 従来困難だった複雑形状部品の製造 – 設計の自由度向上 |
より効率的な製造 |
| 仮想現実・拡張現実の活用 | – 仮想空間での設計モデルの3次元確認 – 製造工程のシミュレーション |
設計・製造の効率化 |
