不正アクセスを防ぐための対策

ITを学びたい
「不正アクセス」って、具体的にどんなことをするんですか?

IT専門家
そうですね。例えば、他人のパスワードを盗み見て、許可なくコンピューターを使ったり、データを覗いたり、書き換えたりすることです。クレジットカード番号などの個人情報を盗むのも不正アクセスにあたります。

ITを学びたい
パスワードを知らなくても不正アクセスになる場合はありますか?

IT専門家
はい。不正な方法でパスワードを手に入れることも不正アクセスです。例えば、他人を騙してパスワードを聞き出したり、コンピューターのシステムの弱点を探して侵入したりするのも含まれます。許可なくコンピューターを操作することが、不正アクセスにあたるんですよ。
不正アクセスとは。
許可されていない人が、コンピューターやコンピューターのネットワークを不正に利用したり、利用しようとしたりする行為について説明します。これは『不正アクセス』と呼ばれるものです。不正な方法でパスワードを手に入れて、ファイルをこっそり見たり、書き換えたりする行為や、クレジットカード番号などの個人の情報を盗む行為などが含まれます。日本では、このような行為を禁止する法律として、不正アクセス禁止法が平成12年(2000年)に施行されました。
不正アクセスの概要
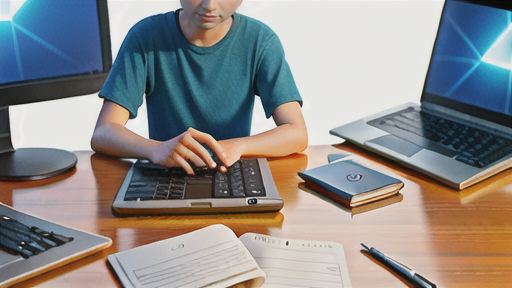
許可なく他人の計算機や情報網に侵入する行為を不正アクセスと言います。これは、まるで鍵の掛かっていない家に勝手に侵入し、家財道具を盗んだり壊したりする行為と同じくらい重大な犯罪です。他人の計算機や情報網に許可なく入り込み、情報を盗み見たり、書き換えたり、仕組み全体を壊したりする行為は全て不正アクセスに当たります。
近年、情報網の普及に伴い、不正アクセスの件数は増加の一途を辿っています。企業だけでなく、個人にとっても大きな脅威となっています。例えば、買い物をする際に利用する情報網の販売サイトや、個人が利用する情報網の記録場所に不正にアクセスされ、個人情報や金銭に関する情報が盗まれる危険性があります。また、企業の情報網に不正アクセスされると、顧客の情報が漏洩したり、会社の機密情報が盗まれたりする恐れがあります。このような被害は、経済的な損失だけでなく、社会的な信用を失墜させることにも繋がりかねません。
不正アクセスは、単に情報が漏れるだけにとどまらない深刻な被害をもたらします。例えば、企業の事業が停止したり、顧客からの信頼を失って倒産に追い込まれることもあります。また、個人の場合も、金銭的な被害だけでなく、プライバシーが侵害され、精神的な苦痛を受けることもあります。さらに、不正アクセスされた計算機を踏み台にして、別の犯罪が行われる可能性もあります。例えば、大量の迷惑な手紙を送りつけたり、他の計算機を攻撃する拠点として利用されたりすることもあります。
だからこそ、不正アクセスを防ぐための対策は、現代社会において欠かすことができません。複雑な合い言葉を設定したり、安全な情報網を利用したり、怪しい手紙を開かないようにするなど、一人ひとりが注意を払う必要があります。また、企業も、従業員への教育や、安全な仕組みの構築など、組織的な対策を講じる必要があります。不正アクセスから自分自身を守り、安全な情報社会を築くためには、一人ひとりの意識と行動が重要です。
| 不正アクセスとは | 不正アクセスの影響 | 不正アクセスの対策 |
|---|---|---|
| 許可なく他人の計算機や情報網に侵入する行為。 情報を盗み見たり、書き換えたり、仕組み全体を壊したりする行為は全て不正アクセスに当たる。 |
|
|
不正アクセスの種類

許可されていない者が、他人の情報機器やネットワークに侵入することを不正アクセスといいます。これは、建物の鍵を壊して侵入する行為と同様に、重大な犯罪です。不正アクセスには様々な種類があり、その手口も複雑化しています。まず、よく知られているのが「暗証番号解読」です。これは、様々な方法で他人の暗証番号を盗み見て、情報機器などに不正に侵入する行為です。総当たりで暗証番号を試したり、盗聴器などで入力の様子を盗み見たり、巧妙な方法を用いて暗証番号を盗み取ります。
次に、「機構の欠陥攻撃」があります。これは、情報機器やネットワークの仕組みの弱点を探し出し、そこを突いて侵入する高度な技術を用いた行為です。システムの不備を悪用して、本来アクセスできない場所に侵入を試みます。
また、「身分偽装」も不正アクセスのひとつです。これは、正規の利用者のふりをして、情報機器やネットワークにアクセスする行為です。他人の利用者識別符号や暗証番号を盗用し、あたかも正規の利用者のように振る舞って侵入します。近年増加しているのが、「悪意ある仕掛け攻撃」です。これは、情報機器やネットワークに侵入するために、特殊な仕掛けを用いる攻撃です。例えば、情報機器に害を及ぼす小さな仕掛けを仕込んだり、そうした仕掛けを送りつけて相手の機器を乗っ取ったりします。
さらに、最近では「人間心理の悪用」という巧妙な手口も増えています。これは、人間の心理的な隙を突いて、暗証番号などの重要な情報を騙し取る行為です。偽の連絡先を作って本物そっくりの偽画面を表示させ、暗証番号を入力させて盗み取ったり、電話で個人情報を聞き出したりするなど、巧妙な手口で個人情報を狙ってきます。これらの不正アクセスから身を守るためには、それぞれの攻撃手法に合わせた対策が必要です。例えば、暗証番号は推測されにくい複雑なものにする、機構の欠陥を修正するプログラムを常に最新の状態に保つ、怪しい連絡先にはアクセスしない、個人情報を安易に教えないなど、日頃から警戒を怠らないことが重要です。
| 不正アクセスの種類 | 説明 |
|---|---|
| 暗証番号解読 | 様々な方法で他人の暗証番号を盗み見て、情報機器などに不正に侵入する行為。 |
| 機構の欠陥攻撃 | 情報機器やネットワークの仕組みの弱点を探し出し、そこを突いて侵入する高度な技術を用いた行為。 |
| 身分偽装 | 正規の利用者のふりをして、情報機器やネットワークにアクセスする行為。 |
| 悪意ある仕掛け攻撃 | 情報機器やネットワークに侵入するために、特殊な仕掛けを用いる攻撃。 |
| 人間心理の悪用 | 人間の心理的な隙を突いて、暗証番号などの重要な情報を騙し取る行為。 |
不正アクセスによる被害

不正アクセスによる被害は、私たちの暮らしや仕事に様々な形で影響を及ぼします。個人情報の流出は、不正アクセスでもっとも懸念される被害の一つです。氏名や住所、電話番号といった基本的な情報だけでなく、クレジットカード番号や銀行口座情報、さらには健康情報といった非常に個人的な情報までが、流出の危険に晒されています。これらの情報が悪用されると、クレジットカードの不正利用やネットショッピングでのなりすまし被害といった金銭的な損害だけでなく、個人になりすまして様々な犯罪行為が行われる可能性も出てきます。また、企業にとっては、業務に関する重要な情報や顧客情報、取引先情報などの機密情報の流出は、事業活動に深刻な支障をきたす恐れがあります。競合他社に重要な情報が渡ってしまえば、競争上の優位性を失い、市場シェアの低下や利益の減少につながる可能性があります。また、顧客情報が流出すれば、顧客からの信頼を失い、企業イメージの低下は避けられません。これは、企業の存続に関わる重大な問題になりかねません。加えて、不正アクセスによってシステムが破壊されると、業務が停止に追い込まれることもあります。会社のネットワークが使えなくなったり、ウェブサイトが閲覧できなくなったりすることで、通常の業務が滞り、取引先や顧客に多大な迷惑をかけることになります。その結果、取引停止や契約解除といった事態に発展する可能性も否定できません。システムの復旧にも時間と費用がかかり、企業の財政を圧迫する要因となります。不正アクセスが発覚すれば、企業の信頼は大きく損なわれ、社会的な制裁を受ける可能性も出てきます。顧客や取引先からの信頼を失い、将来のビジネスチャンスを失うだけでなく、株価の下落や投資家の撤退といった経済的な損失も招く恐れがあります。これらの被害は、企業の規模に関わらず発生する可能性があり、個人と企業の双方にとって、不正アクセス対策は必要不可欠です。
| 被害者 | 不正アクセスによる被害 | 影響 |
|---|---|---|
| 個人 | 個人情報の流出 (氏名、住所、電話番号、クレジットカード番号、銀行口座情報、健康情報など) |
|
| 企業 |
|
|
不正アクセス対策の重要性

情報網が社会の基盤としてなくてはならないものになった現代において、不正なアクセスを防ぐことの大切さは、ますます大きくなっています。もはや情報網は、私たちの生活や仕事に欠かせないものとなっています。企業も個人も、情報網を通じて様々な活動を行っています。しかし、それと同時に、情報網を通じた犯罪や攻撃の危険性も高まっています。中でも、不正なアクセスは、大きな脅威となっています。不正アクセスとは、許可なく他人の情報網や計算機に侵入することです。これは、法律で禁じられており、罰せられる可能性があります。
企業にとっては、顧客の情報や会社の機密情報など、大切な情報を守るために、適切な安全対策を講じることが必要です。もし、これらの情報が不正アクセスによって盗まれたり、壊されたりすると、会社は大きな損害を被る可能性があります。顧客からの信頼を失うだけでなく、会社の評判にも大きな傷がつくでしょう。また、法律に基づいて罰せられる可能性もあります。そのため、企業は、防火壁の設置や侵入検知システムの導入など、様々な安全対策を講じる必要があります。さらに、社員への安全教育も重要です。社員一人ひとりが安全意識を高め、適切な行動をとることで、不正アクセスを防ぐことができます。
個人にとっても、自分の個人情報が漏れないように、自ら対策を講じることが重要です。例えば、パスワードをしっかりと管理したり、安全対策用の道具を導入したりする必要があります。パスワードは、推測されにくい複雑なものにし、定期的に変更することが重要です。また、安全対策用の道具は、常に最新の状態に保つ必要があります。不正アクセスは、いつ、どこで、誰に起こるかわかりません。常に安全意識を高め、適切な対策を講じることが大切です。
そのためには、日頃から安全に関する情報を集め、最新の脅威や対策方法を理解しておくことが重要です。安全に関する情報は、様々な場所で入手できます。例えば、国の機関や安全対策の専門会社が提供する情報網の場所や、書籍、雑誌などがあります。また、周りの人々から情報を得ることもできます。これらの情報を活用し、常に最新の知識を身につけることで、不正アクセスによる被害を防ぐことができます。安全対策は、一度行えば終わりではありません。常に変化する脅威に対応するために、継続的な努力が必要です。
| 対象 | 不正アクセスの脅威 | 対策 |
|---|---|---|
| 企業 | 顧客情報、機密情報の漏洩・破壊、経済的損失、風評被害、法的責任 | 防火壁、侵入検知システム、社員教育 |
| 個人 | 個人情報の漏洩 | パスワード管理、セキュリティソフト導入 |
| 共通 | – | 情報収集、最新脅威と対策方法の理解、継続的な努力 |
具体的な対策方法

不正なアクセスを防ぐには、いくつもの対策を組み合わせることが肝心です。その一つとして、合い言葉は、他人に推測されにくい複雑なものにして、定期的に変更することが大切です。推測されやすい簡単な合い言葉は、まるで鍵のかかっていない玄関のようなものです。泥棒に簡単に侵入されてしまう危険があります。複雑な合い言葉を設定し、定期的に変更することで、不正アクセスされる危険性を減らすことができます。
次に、家の塀のような役割を果たす「防火壁」や、家の警備員のような「安全対策用の道具」を導入し、常に最新の状態に保つことも重要です。防火壁は、外部からの不正アクセスを遮断する役割を果たし、安全対策用の道具は、コンピュータウイルスなどの脅威から守ってくれます。これらを常に最新の状態に更新することで、最新の脅威にも対応できるようになります。古くなった道具では、新しい型の泥棒には効果がありません。
また、使っている機械や道具の弱点を取り除くために、定期的に更新作業を行う必要があります。弱点があると、そこを突かれて不正アクセスされてしまう可能性があります。こまめな更新作業は、家の修理や補強と同じように、安全性を高めるために欠かせません。
さらに、巧妙な嘘や策略で個人情報を盗み取る「策略による情報詐取」のような手口に騙されないように注意することも大切です。怪しい手紙や場所にアクセスしない、個人情報を簡単に教えないなど、用心深さが重要です。甘い言葉に誘われて不用意にドアを開けてしまうと、泥棒を家の中に招き入れてしまうのと同じです。
これらの対策を行うことで、不正アクセスされる危険性を大幅に下げることができます。安全対策は、一度行えば終わりではなく、常に最新の状態を保つことが大切です。家の安全を守るためには、常に鍵を最新のものに交換したり、警備システムを最新の状態に保ったりする必要があるのと同じです。
また、一緒に働く人への安全に関する教育も重要です。安全に対する意識を高め、正しい行動をとるように指導することで、不正アクセスを防ぐことができます。全員が安全意識を持って行動することで、より安全な環境を作ることができるのです。
| 対策 | 説明 | 例え |
|---|---|---|
| 複雑な合い言葉設定と定期的な変更 | 他人に推測されにくい複雑な合い言葉を設定し、定期的に変更する。 | 家の鍵を複雑なものにし、定期的に交換する。 |
| 防火壁と安全対策用道具の導入と更新 | 外部からの不正アクセスを遮断する防火壁や、コンピュータウイルスから守る安全対策用道具を導入し、常に最新の状態に保つ。 | 家の塀(防火壁)や家の警備員(安全対策用道具)を配置し、常に最新の状態にする。 |
| 機械や道具の定期的な更新 | 使っている機械や道具の弱点を取り除くために、定期的に更新作業を行う。 | 家の修理や補強を行う。 |
| 策略による情報詐取への注意 | 巧妙な嘘や策略で個人情報を盗み取る「策略による情報詐取」のような手口に騙されないように注意する。 | 甘い言葉に誘われて不用意にドアを開けない。 |
| 安全に関する教育 | 一緒に働く人への安全に関する教育を行い、安全に対する意識を高め、正しい行動をとるように指導する。 | 家族全員に家の安全を守るためのルールを教え、実践させる。 |
法的な対応

私たちの暮らしの中で、情報を取り扱う機器を使う機会が増えています。それと同時に、許可なく他人の情報機器にアクセスする、不正アクセスという問題も深刻になっています。日本では、このような不正アクセスを防ぐために、「不正アクセス禁止法」という法律が作られています。
この法律では、他人の情報機器にアクセスする行為を不正アクセスと定義し、罰則を設けています。例えば、正当な理由なく他人の情報機器にアクセスした場合、10年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。また、侵入した情報機器から情報を盗み出した場合、さらに重い罰則が適用されることもあります。不正アクセスは決して軽い気持ちで行っていいものではなく、重大な犯罪行為です。
もし、あなたが不正アクセスをしてしまった場合、法律に基づいて罰せられる可能性があります。また、不正アクセスによって誰かに損害を与えた場合、損害賠償を請求されることもあります。不正アクセスは自分自身だけでなく、周りの人々にも大きな迷惑をかける行為です。
反対に、もしあなたが不正アクセスの被害にあった場合、警察に相談し、被害届を出すことができます。証拠となるものがあれば、それも一緒に提出しましょう。専門の捜査員が調査を行い、犯人を特定し、適切な処罰を行います。
不正アクセスは、私たちの情報社会にとって大きな脅威です。一人ひとりが情報機器の適切な使い方を学び、安全な使い方を心がけることが大切です。パスワードをしっかり管理したり、怪しい通信には注意したりするなど、基本的な対策をしっかりと行うことで、不正アクセスから身を守り、安全な情報社会を作っていくことができます。
| 行為 | 罰則 |
|---|---|
| 正当な理由なく他人の情報機器にアクセス | 10年以下の懲役または500万円以下の罰金 |
| 侵入した情報機器から情報を盗み出す | さらに重い罰則 |
| 不正アクセスをしてしまった場合 | 法律に基づいて罰せられる可能性、損害賠償請求の可能性 |
|---|---|
| 不正アクセスの被害にあった場合 | 警察に相談、被害届の提出 |
| 情報機器の適切な使い方 | パスワードのしっかりとした管理、怪しい通信への注意 |
|---|
