SCSI:周辺機器接続の古豪

ITを学びたい
先生、「SCSI」って聞いたことはあるんですけど、どんなものかよくわからないんです。教えてもらえますか?

IT専門家
SCSIは、コンピューターと周辺機器をつなぐための規格のひとつだよ。昔は、パソコンとハードディスクやプリンターなどを繋ぐ時によく使われていたんだ。

ITを学びたい
今はもう使われていないんですか?

IT専門家
今はUSBやIEEE1394といった規格が主流になってきているから、SCSIを見る機会は少なくなったね。でも、SCSIは高速で汎用性が高いように改良された後継規格もあるんだよ。
SCSIとは。
情報技術に関する言葉「スカジー」について説明します。スカジーとは、コンピューターと周辺機器をつなぐための規格の一つです。アメリカの規格協会が定めました。より速く、より広く使えるように改良された規格も出てきました。スカジーは、主にパソコンとハードディスク、スキャナー、プリンターなどをつなぐために使われていましたが、2000年ごろから、USBやIEEE1394(アイ・トリプル・イー・いちさんきゅうよん)が主流になりました。スカジーという言葉は、「スモール・コンピューター・システム・インターフェース」のそれぞれの言葉の頭文字をとったものです。
SCSIとは

小型計算機機構接続方式(SCSIと略します)は、計算機と周辺機器を繋ぐための規格です。「スカジー」と読みます。米国規格協会が定めたもので、以前はパソコンと固定記憶装置、画像読み取り装置、印刷装置などを繋ぐ主要な手段として広く使われていました。SCSIは、速い情報伝達と様々な機器への対応が特徴で、業務用の計算機や高性能のパソコンなどで特に重宝されました。様々な機器を一本のSCSIの線で繋げるので、配線の苦労を減らすことができました。
SCSIが出始めた頃は、パソコンに周辺機器を繋ぐ標準的な規格が定まっておらず、様々な規格が乱立していました。SCSIはそのような中で、速さと汎用性を武器に広まりました。特に、固定記憶装置のような大きな情報のやり取りをする機器との接続では、SCSIの速さが大きな利点となりました。また、SCSIは複数の機器を同時に繋げるので、機構の拡張性にも優れていました。
SCSIは、様々な種類があり、それぞれ伝達速度や接続方法などが違います。初期のSCSIは並列に情報を伝達する方式でしたが、技術の進歩とともに、より速く情報を伝達できるシリアル方式のSCSIも登場しました。シリアル方式のSCSIは、ファイバーチャネルやSAS(サス)と呼ばれ、現在でも大規模な計算機機構などで使われています。
SCSIは、以前はパソコンの周辺機器接続の主流でしたが、近年はUSBやシリアルATAといった新しい規格に取って代わられています。これらの新しい規格は、SCSIよりも安価で使いやすいため、パソコンだけでなく、様々な電子機器で広く使われています。しかし、SCSIは高い信頼性と速さを持ち、現在でも一部の業務用機器や高性能な計算機などで使われ続けています。時代に合わせて変化しながら、SCSIは計算機の歴史の中で重要な役割を果たしてきたと言えます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 小型計算機機構接続方式(SCSI、スカジー) |
| 目的 | 計算機と周辺機器の接続 |
| 規格制定 | 米国規格協会 |
| 特徴 | 高速な情報伝達、多様な機器への対応、複数機器の同時接続 |
| 利点 | 配線の手間削減、大容量データ転送に有利、拡張性が高い |
| 種類 | 並列方式、シリアル方式(ファイバーチャネル、SAS) |
| 現状 | USBやシリアルATAに置き換えられつつあるが、一部の業務用機器や高性能計算機では現役 |
規格の進化

情報を伝えるやり方の決まり事、つまり規格は、時代と共に大きく変わってきました。この変化は、まるで生き物の進化のようです。特に、コンピュータの中の部品をつなぐ規格の一つである「SCSI」規格の進化は目覚ましいものがあります。
最初のSCSI規格は、比較的速度が遅く、できることも限られていました。しかし、技術の進歩と共に、より速く、より多くのことができるように改良が加えられていきました。「速いSCSI」という意味の「Fast SCSI」を皮切りに、「超SCSI」を意味する「Ultra SCSI」、「Ultra2 SCSI」、「Ultra3 SCSI」、「Ultra320 SCSI」など、様々な改良型が登場しました。これらの新しい規格は、前のものよりも速く情報を送れるだけでなく、一度にたくさんの機器をつなげたり、機器と機器の間を長い線でつないだりできるようになりました。
例えば、「Ultra SCSI」は、それまでのSCSIに比べて2倍の速さで情報を送ることができました。「Ultra2 SCSI」はさらにその速さを2倍にし、「Ultra SCSI」の4倍もの速さを実現しました。このように、SCSI規格は常に新しい技術を取り入れ、より高性能な仕組みを作るために進化を続けてきました。
その後、SCSI規格は大きな転換期を迎え、「SAS」という新しい規格が登場しました。「SAS」は、「直列接続SCSI」という意味で、従来の並列接続方式から直列接続方式へと変更されました。この変更により、SCSIはさらに高速で安定したデータ転送を実現し、より多くの機器を接続することが可能になりました。まるで生き物が環境に合わせて姿を変えるように、SCSI規格も時代のニーズに合わせて変化し続けてきたのです。この絶え間ない進化こそが、SCSI規格が長年にわたって多くの利用者に選ばれてきた大きな理由と言えるでしょう。
| 規格名 | 特徴 |
|---|---|
| 初期のSCSI | 速度が遅く、機能も限定的 |
| Fast SCSI | 初期のSCSIより高速化 |
| Ultra SCSI | Fast SCSIの2倍の速度 |
| Ultra2 SCSI | Ultra SCSIの2倍(Fast SCSIの4倍)の速度 |
| Ultra3 SCSI | Ultra2 SCSIより高速化 |
| Ultra320 SCSI | Ultra3 SCSIより高速化 |
| SAS (Serial Attached SCSI) | 直列接続方式に変更、高速かつ安定したデータ転送、多数の機器接続が可能 |
USB、IEEE1394との競合

かつて、周辺機器を計算機につなぐ際には、主に「小型計算機システム接続機構(SCSI)」と呼ばれる規格が用いられていました。ところが、2000年頃を境に、新たな接続規格が登場し、主役の座を奪うことになります。それが「汎用直列バス(USB)」と「IEEE1394」です。
SCSIは、高速なデータ転送速度を誇り、高性能な機器を接続するのに最適でした。しかし、その反面、機器の値段や接続の複雑さ、そして計算機の電源を切らないと機器を接続したり取り外したりできないといった不便さがありました。
一方、新しく登場したUSBとIEEE1394は、SCSIに比べて手軽で安価でした。誰でも簡単に機器を接続することができ、費用も抑えることができたのです。さらに、電源を入れたまま機器の接続や取り外しができる「活線挿抜」にも対応しており、使い勝手も格段に向上しました。例えば、印刷の途中でインクが切れても、計算機の電源を落とさずにインクカートリッジを交換できるといった利便性を提供しました。
これらの新たな規格は、家庭用計算機の普及と共に急速に広まりました。特にUSBは、様々な機器に対応し、広く普及しました。マウスやキーボード、印刷機、記憶装置など、多種多様な機器がUSBで接続できるようになり、家庭用計算機にはなくてはならない存在となりました。IEEE1394は、動画の編集など、高速なデータ転送が必要な場面で使われることが多かったものの、USBほどの普及は見られませんでした。
このように、手軽さ、安価さ、そして使い勝手の良さという点で、USBとIEEE1394はSCSIを凌駕し、SCSIは次第に家庭用計算機市場から姿を消していきました。SCSIは、高性能な機器を必要とする一部の専門分野で使われ続けるものの、主流の座からは降りることになったのです。
| 項目 | SCSI | USB | IEEE1394 |
|---|---|---|---|
| データ転送速度 | 高速 | SCSIより低速 | 高速 |
| 価格 | 高価 | 安価 | 安価 |
| 接続の複雑さ | 複雑 | 簡単 | 簡単 |
| 活線挿抜 | 不可 | 可 | 可 |
| 普及率 | 家庭用では衰退 | 広く普及 | USBほど普及せず |
| 用途 | 高性能機器 | 多種多様な機器 | 高速データ転送が必要な機器 |
SCSIの利点と欠点

小さなコンピュータシステム同士を繋ぐ技術の一つであるSCSIは、良いところと悪いところを併せ持っています。
まず、SCSIの長所を見ていきましょう。SCSIは情報のやり取りがとても速いことが挙げられます。特に、大きな計算をするコンピュータや絵を描くコンピュータなどで、この速さは大きな力を発揮します。たくさんの情報を素早く処理する必要があるため、SCSIの速さは作業の効率を大きく高めます。また、様々な機器に対応できることも利点です。色々な機器を繋ぐことができるので、システム全体を柔軟に構築できます。加えて、安定して動作することもSCSIの強みです。情報のやり取りが安定しているため、安心してシステムを運用できます。
一方で、SCSIには短所も存在します。他の接続方法と比べると価格が高いことが欠点として挙げられます。USBやIEEE1394といった接続方法はSCSIより安価なため、予算を抑えたい場合にはSCSIは不向きです。また、機器を繋ぐ設定が複雑という問題もあります。専門的な知識が必要な場合もあり、初めての人にとっては難しいと感じるかもしれません。さらに、SCSIの接続に使う線は太くて硬く、場所をとるため、機器の配置や配線を考える際に苦労する可能性があります。線が絡まりやすく、整理が大変になることもあるでしょう。このように、SCSIは速くて安定した情報のやり取りが可能である反面、価格や設定の複雑さ、線の取り回しなどに課題があると言えます。
| SCSIのメリット | SCSIのデメリット |
|---|---|
| 情報のやり取りが速い | 価格が高い |
| 様々な機器に対応できる | 機器を繋ぐ設定が複雑 |
| 安定して動作する | 線が太くて硬く、場所をとる |
SCSIの現状
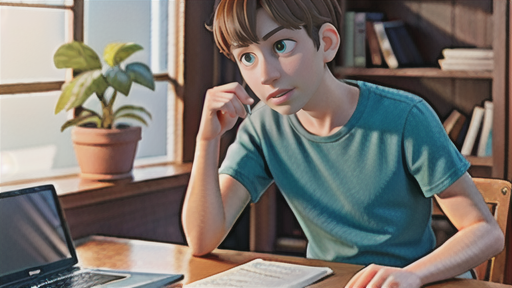
少し前まではコンピュータの周辺機器をつなぐ方法としてSCSIが広く使われていました。しかし、時代は変わり、今ではUSBやIEEE1394、SATAといった規格が主流となり、SCSIを見かける機会は少なくなりました。とはいえ、SCSIが完全に消えてしまったわけではありません。高い信頼性と処理速度が求められる場面では、今でもSCSIは活躍しています。特に、企業で使われるような重要なシステムでは、安定してしっかり動くことが大切です。そこで、長年の実績と信頼性を持つSCSIが選ばれているのです。
SCSIは、時代に合わせて進化も遂げています。SAS(サス)と呼ばれる技術は、SCSIの優れた点を引き継ぎながら、より速いデータのやり取りを可能にしました。データを一列に並べて送ることで、従来のSCSIよりも効率的に情報を伝えることができるのです。このSASは、多くの情報を扱う必要がある会社のコンピュータで中心的な役割を担っています。つまり、SCSIは姿を変えながら、今でも重要な技術として使われ続けているのです。
特に、大量のデータを読み書きする必要があるサーバー用途では、SCSIの安定した動作は大きな魅力です。少しのエラーでも大きな問題につながる可能性があるため、信頼性が何よりも重視されます。また、動画編集や科学技術計算などの専門的な分野でも、SCSIの高速なデータ転送能力は欠かせません。これらの分野では、巨大なファイルを扱うことが多く、少しでも処理速度が速いことが求められます。このように、SCSIは最先端技術ではなくなりましたが、特定の分野では今でもなくてはならない存在であり続けています。時代とともに形を変えながら、進化を続けるSCSIの技術は、これからも私たちの生活を支えていくことでしょう。
| SCSIの特徴 | メリット | 用途 |
|---|---|---|
| 高い信頼性 | 安定した動作 | 企業の重要なシステム、サーバー |
| 高速な処理速度 | 効率的なデータ転送 | 動画編集、科学技術計算 |
| 進化形: SAS | 従来のSCSIよりも高速なデータ転送 | 大量の情報を扱う企業のコンピュータ |
まとめ

小さなコンピューターシステムインタフェース、略してスカジーは、かつてはパソコンと周辺機器、例えばプリンターや記憶装置などを繋ぐ主要な方法として広く使われていました。この接続方法は、情報のやり取りが速いことと、様々な機器に対応できることから、多くの利用者に選ばれていました。
時代が進むにつれて、スカジーも進化を続け、様々な改良版が登場しました。しかし、USBやアイ・トリプル・イー1394といった新しい規格が登場すると、スカジーは徐々に主役の座を譲ることになりました。これらの新しい規格は、スカジーよりも使い勝手が良く、より多くの機器に対応できるようになっていました。
とはいえ、スカジーの技術が完全に消えてしまったわけではありません。シリアル接続スカジー、略してサスといった後継の規格に受け継がれ、今でも特定の分野で使われ続けています。特に、企業向けの大規模なコンピューターシステムなどでは、サスがその信頼性と高速性から重要な役割を担っています。
スカジーの歴史を振り返ることで、コンピューター技術がどのように発展してきたのかを知ることができます。スカジーは、高速性と汎用性を両立させた先駆的な技術であり、その後のコンピューター技術の発展に大きな影響を与えました。今では主流ではなくなりましたが、その技術は形を変えて現在も生き続けているのです。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| スカジー (SCSI) | 小さなコンピュータシステムインタフェース。かつてパソコンと周辺機器を繋ぐ主要な方法。情報のやり取りが速く、様々な機器に対応できた。 |
| 利点 | 高速なデータ転送、多様な機器への対応 |
| 衰退の理由 | USBやIEEE1394といった、より使い勝手が良く、多くの機器に対応できる規格の登場。 |
| 後継規格 | シリアル接続スカジー (SAS)。特に企業向けの大規模なコンピュータシステムで利用。 |
| 現在の状況 | 主流ではなくなったが、技術は形を変えて現在も生き続けている。 |
