情報共有の要:共有フォルダー

ITを学びたい
先生、『共有フォルダー』って、みんなで使えるフォルダーのことですよね?

IT専門家
そうだね。ネットワークにつながっている複数のパソコンから、同じフォルダーの中身を見たり、書き込んだりできるフォルダーのことだよ。

ITを学びたい
じゃあ、自分のパソコンにあるファイルやフォルダーをみんなが勝手に触れるってことですか?

IT専門家
そういうことではないよ。共有フォルダーには『読み取り専用』などのアクセス権を設定できる。権限によって、見ることができるだけの人、書き込みや削除ができる人などを決められるんだ。
共有フォルダーとは。
コンピューター同士が繋がる仕組み(いわゆるランなど)の中で、複数の人が同じ場所にある書類入れを覗いたり、使ったりできるように設定することを「共有フォルダー」と言います。この「共有フォルダー」は「共有ディレクトリー」と呼ばれることもあります。
共有フォルダーとは

共同で使う場所、それが共有保存場所です。 ちょうど、家族みんなで使う家の棚を想像してみてください。棚には書類やアルバムなど、家族みんなが使うものが置いてありますよね。誰でも必要な時に棚から物を取り出したり、逆に使わなくなった物をしまったりすることができます。これと同じように、計算機の世界にも、みんなで使える場所があります。それが共有保存場所です。
共有保存場所は、計算機同士が繋がる網の目のような場所に作られます。 この網の目を通り、許可された人だけが保存場所にあるデータを見たり、書き換えたり、新しいデータを追加したりできます。まるで、家の鍵を持っている家族だけが家に入れるのと同じです。
この仕組みのおかげで、複数人で一緒に仕事をするのがずっと楽になります。 例えば、みんなで一緒に資料を作る場合を考えてみましょう。資料を共有保存場所に置いておけば、それぞれが自分の計算機から最新の資料を開いて、自分の担当部分を書き加えることができます。いちいち資料を写した記憶装置をやり取りする必要はありません。
会議で使う資料なども、共有保存場所に置いておくことで、参加者全員が同じ資料を見ることができます。 資料を印刷して配ったり、参加者それぞれに資料を送ったりする手間が省け、準備もスムーズになります。また、資料に変更があった場合でも、共有保存場所にある資料を更新するだけで、全員が最新の資料を参照できるため、情報の行き違いを防ぎ、円滑な共同作業を実現できます。
| 概念 | 説明 | メリット |
|---|---|---|
| 共有保存場所 | 複数人でアクセスできる、ネットワーク上の保存場所。許可されたユーザーがデータの閲覧、編集、追加を行うことができる。 | 共同作業の効率化、情報の共有、資料の配布・管理の手間削減、情報の行き違い防止 |
| アクセス制御 | 家の鍵のように、許可されたユーザーのみがアクセス可能。 | データのセキュリティ確保 |
| 共同作業 | 資料の共同編集、会議資料の共有などが容易になる。 | 作業効率向上、情報共有の促進、スムーズな会議運営 |
共有フォルダーの利点
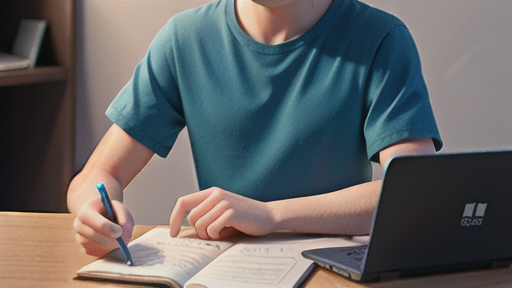
情報をみんなで扱う場合、共有場所を作ることで多くの良い点があります。まず、情報のやり取りがとても楽になります。電子郵便で書類を送る場合、書類の大きさに制限があったり、どの書類が最新版か分からなくなることがあります。しかし、共有場所を使えば、大きな書類でも簡単に送ることができ、常に最新の情報を見ることができます。
次に、仕事の効率が上がります。複数人で同じ書類を扱う場合、共有場所は大変便利です。それぞれが自分の場所で共有場所にある書類を開き、作業することで、情報がバラバラになることなく、スムーズに仕事を進めることができます。例えば、会議の資料を共有場所に置いておけば、参加者全員が同じ資料を見ながら会議を進めることができます。変更があった場合も、すぐに共有場所に反映されるので、情報の伝達漏れや誤解を防ぐことができます。
さらに、情報を一か所にまとめて管理できるようになります。部署や班で使う資料や情報を共有場所に集めておくことで、情報が散らばるのを防ぎ、必要な情報をすぐに見つけることができます。どこに何があるか分からなくなる、という事態を避けることができます。また、アクセス権を設定することで、限られた人だけが情報を見られるようにすることもできます。これにより、情報の管理が楽になり、安全にも配慮することができます。例えば、顧客情報のような大切な情報を共有場所に保管する場合、アクセス権を設定することで、担当者以外は情報を見られないようにすることができます。
| メリット | 説明 | 具体例 |
|---|---|---|
| 情報のやり取りが楽になる |
|
電子メールでのファイルサイズ制限やバージョン管理の問題を解消 |
| 仕事の効率が上がる |
|
会議資料の共有、リアルタイムでの変更反映 |
| 情報の一元管理 |
|
部署内資料の共有、顧客情報のアクセス制限 |
共有フォルダーの設定方法

複数の機械で資料や情報を共有するために、共同で使える場所を作ることを『共有場所設定』と言います。この設定方法は、機械の種類によって多少違いますが、基本的な流れは同じです。まず、共有したい場所を選びます。これは、書類入れのようなものです。次に、その場所の設定画面を開きます。この設定画面で、誰と共有するか、どのように使わせるかを決めます。
共有する相手は、個人名やグループ名で指定できます。例えば、特定の人にだけ使わせたい場合は、その人の名前を指定します。グループで共有したい場合は、グループ名を指定します。誰とでも共有したい場合は、『全員』を指定します。
次に、アクセス権限を設定します。アクセス権限とは、共有場所への読み書きなどの許可設定のことです。例えば、『見るだけ』に設定すると、相手はその場所にある情報を見ることだけできます。変更や削除はできません。『見る』『書き込む』の両方を許可すると、相手は情報を見たり、変更したり、新しく追加したりできます。このように、必要に応じて細かく設定できます。設定が終わったら、共有場所が正しく使えるか確認しましょう。他の機械から接続できるか、設定した権限が正しく機能しているかなどを確かめます。機械の種類によっては、設定後すぐに反映されない場合もあるので、少し時間を置いてから確認する必要があるかもしれません。より詳しい設定方法は、それぞれの機械の説明書や案内を参照することをお勧めします。
| 設定項目 | 詳細 |
|---|---|
| 共有場所の選択 | 共有したいフォルダやドライブを選択 |
| 共有相手の設定 |
|
| アクセス権限の設定 |
必要に応じて細かく設定可能 |
| 動作確認 |
|
共有フォルダーの注意点

複数の利用者が資料や情報をやり取りする際に便利な共有場所は、安全管理にも気を配る必要があります。アクセスできる人を適切に設定しないと、許可されていない人が覗き見たり、大切な情報を持ち出したりする危険があります。まるで自宅の鍵のように、誰が入れるかをきちんと管理する必要があります。具体的には、閲覧だけ許可する、変更も許可する、あるいは全くアクセスできないようにするなど、資料の重要度や利用者の役割に応じて細かく設定することが重要です。さらに、共有場所に保管する情報によっては、鍵となる暗号を設定することも有効な手段です。
また、共有場所には保管できる量が決まっています。たくさんの資料を保存し続けると、いっぱいになって新しい資料が保存できなくなる可能性があります。これは、倉庫に荷物を詰め込みすぎると、新しい荷物が入りきらなくなるのと同じです。ですので、不要になった資料は定期的に整理して削除したり、大きなサイズの資料は圧縮して小さくしたりするなど、日頃から整理整頓を心がけることが大切です。
さらに、もしもの時に備えて予備の保管場所を確保することも忘れてはいけません。共有場所に保管されている情報が、何らかの原因で失われてしまう可能性もゼロではありません。これは、お店が火事になって商品が全て燃えてしまうようなものです。このような事態に備えて、定期的に情報を別の場所に複製しておくことが重要です。複製した情報は、持ち運びできる記録装置やインターネット上の保管場所など、複数の場所に保管しておくことがより安心です。大切な情報を守るためには、安全対策、容量管理、そして複製、この三つをしっかりと意識することが重要です。
| 項目 | 説明 | 例え |
|---|---|---|
| アクセス制御(安全管理) | アクセス権限を適切に設定し、許可されていないアクセスを防ぐ。閲覧、変更、アクセス不可など、重要度や役割に応じて設定。必要に応じて暗号化も検討。 | 自宅の鍵:誰が入れるかを管理する |
| 容量管理(保管できる量) | 保管容量に限りがあるため、不要な資料の削除、ファイルの圧縮など、整理整頓を心がける。 | 倉庫:荷物を詰め込みすぎると新しい荷物が入らない |
| バックアップ(予備の保管場所) | 万が一のデータ損失に備え、定期的にデータを複製し、複数の場所に保管する。 | お店が火事:商品が全て燃えてしまう |
共有フォルダーの活用事例

共有保管場所は、様々な場面で役立っています。職場では、部署内での情報伝達を円滑にするために活用されています。例えば、営業部署では、顧客の情報や提案資料などを共有保管場所に置くことで、担当者同士がすぐに同じ情報にアクセスできるようになり、スムーズな営業活動を実現できます。また、開発部署では、プログラムの設計図や部品となるコードを共有保管場所に保存することで、開発担当者全員が常に最新の情報を共有しながら共同作業を進めることが可能になります。
教育の場でも、教材や課題の受け渡しに活用されています。例えば、先生は生徒に配る資料を共有保管場所に置いておくことで、生徒は自分のパソコンから必要な時に資料をダウンロードできるようになります。これは印刷の手間を省くだけでなく、紙の消費量を減らすことにも繋がります。
家庭でも、家族間の思い出の共有に役立ちます。旅行で撮影した写真や子供の動画を共有保管場所に保存しておけば、家族全員がいつでも好きな時に見返すことができます。また、パソコンだけでなく、携帯端末からもアクセスできるように設定すれば、外出先でも家族の思い出を共有することができます。このように、共有保管場所は、職場や学校、家庭など、様々な場面で情報伝達をスムーズにし、共同作業を効率化するための大切な道具となっています。近年では、インターネットを通じてアクセスできる共有保管場所のサービスも増えており、場所を選ばずに情報共有が可能になっています。こうしたサービスを活用することで、より便利に情報共有を進めることができます。
| 場面 | 活用例 | メリット |
|---|---|---|
| 職場 ・営業部署 |
顧客情報、提案資料の共有 | 担当者間での情報アクセスが容易になり、スムーズな営業活動を実現 |
| 職場 ・開発部署 |
プログラム設計図、コードの共有 | 最新情報の共有、共同作業の効率化 |
| 教育 | 教材、課題の受け渡し | 印刷の手間削減、紙の消費量削減、必要な時にアクセス可能 |
| 家庭 | 写真、動画の共有 | 家族全員がいつでもアクセス可能、思い出の共有 |
