非対称型マルチプロセッシングとは?

ITを学びたい
先生、『非対称型マルチプロセッシング』って、何ですか? よくわからないんですけど…

IT専門家
簡単に言うと、複数の処理装置を役割分担させてコンピュータを動かす方式のことだよ。例えば、一つの処理装置は文字入力を受け付け、もう一つは画面表示の処理をする、といった具合にね。

ITを学びたい
なるほど。複数の処理装置を使うという意味では、『対称型マルチプロセッシング』と同じですよね?何が違うんですか?

IT専門家
いいところに気がついたね。『対称型』の場合は全ての処理装置が同じようにどんな処理でもできる。一方、『非対称型』は、先ほど説明したように、それぞれの処理装置に役割が割り当てられているんだ。だから、役割が固定されている分、処理装置の切り替えにかかる無駄な時間が減って処理速度が向上する、という利点があるんだよ。
非対称型マルチプロセッシングとは。
『情報技術』に関する言葉、『非対称型マルチプロセッシング』(つまり『ASMP』)について
はじめに

計算機の処理能力を高める方法として、複数の処理装置を同時に動かす技術は、今やなくてはならないものとなっています。こうした技術は、複数の処理装置を同時に動かすことから、まとめて複数処理と呼ばれています。複数処理には様々な種類がありますが、今回は非対称型複数処理について説明します。非対称型複数処理とは、それぞれの処理装置に役割を割り当てて動かす方式のことです。それぞれの処理装置に役割を割り当てて動かす方式では、特定の処理装置が全体の制御を担うなど、処理装置ごとに異なる役割を分担します。
この方式は、仕組みが単純なので、設計や実現が比較的容易という利点があります。設計や実現の容易さは、開発期間の短縮や費用の削減に繋がります。また、特定の処理装置に負荷が集中しにくいという特性もあります。これは、システム全体の安定稼働に貢献する重要な要素です。例えば、全体の制御を担う処理装置とは別に、計算処理専用の処理装置を用意することで、制御系の処理に支障をきたすことなく、安定した計算処理を行うことができます。
しかし、処理装置の間で情報のやり取りが必要となるため、通信による遅れが発生する可能性には注意が必要です。処理装置の間で頻繁に情報のやり取りが発生する場合、この遅延がシステム全体の処理速度に影響を与える可能性があります。例えば、ある処理装置が別の処理装置からデータを受け取るまで待機する必要がある場合、その待機時間がシステム全体の処理時間を長くしてしまう可能性があります。そのため、非対称型複数処理を設計する際には、処理装置間の通信量を最小限に抑える工夫や、通信遅延の影響を軽減するための対策を検討する必要があります。具体的には、処理装置ごとに必要な情報をあらかじめ分配しておくなどの対策が考えられます。
| 複数処理の種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 対策 |
|---|---|---|---|---|
| 非対称型複数処理 | 各処理装置に役割を割り当て、特定の処理装置が全体の制御を担う。 |
|
処理装置間での情報やり取りによる通信遅延が発生する可能性がある。 |
|
動作の仕組み

非対称型多重処理方式では、親処理装置と子処理装置という役割分担を持つ複数の処理装置が協調して作業を行います。親処理装置は、指揮者のような役割を担い、システム全体の制御を行います。具体的には、利用可能な資源(記憶領域や周辺機器など)の管理、処理すべき作業の割り当て、処理の進捗状況の監視などを担当します。子処理装置は、作業員のような役割を担い、親処理装置から指示された作業だけを実行します。
親処理装置が全体を管理することで、子処理装置は作業の実行に集中できます。これは、作業の効率を高める上で大きな利点となります。また、各処理装置の役割が明確に分かれているため、システム全体の構造が単純になります。そのため、設計や構築、保守が容易になるという利点もあります。
しかし、この方式には大きな欠点も存在します。親処理装置に障害が発生した場合、システム全体が停止してしまう可能性がある点です。親処理装置はシステム全体の制御を担うため、その信頼性がシステム全体の安定性に直結します。例えるなら、指揮者が倒れてしまうと、オーケストラ全体の演奏が止まってしまうのと同じです。よって、非対称型多重処理方式を採用する際には、親処理装置の信頼性を高めるための対策が不可欠となります。具体的には、予備の親処理装置を用意しておく、定期的に点検を行う、障害発生時に速やかに復旧できる仕組みを構築するなどの対策が考えられます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 処理方式 | 非対称型多重処理方式 |
| 役割分担 | 親処理装置(指揮者):システム全体の制御(資源管理、作業割り当て、進捗監視) 子処理装置(作業員):親処理装置から指示された作業の実行 |
| 利点 | 作業効率の向上、システム構造の単純化(設計、構築、保守が容易) |
| 欠点 | 親処理装置の障害発生時にシステム全体が停止する可能性 |
| 欠点への対策 | 予備の親処理装置、定期点検、障害発生時の迅速な復旧 |
利点

非対称型多重処理方式には、幾つかの利点があります。まず、システムの構造が単純であることが挙げられます。対称型多重処理方式のように、全ての処理装置が同じ役割を持つのではなく、それぞれの処理装置に役割が明確に割り当てられています。この役割分担のおかげで、システムの設計や実現が容易になります。複雑な処理装置間の調整や同期処理などを考える必要がないため、開発期間の短縮や開発費用の削減に繋がります。
次に、システム全体の安定性向上が期待できます。対称型多重処理方式では、特定の処理装置に負荷が集中してしまう可能性があります。しかし、非対称型多重処理方式では、役割ごとに処理装置が割り当てられているため、特定の処理装置への過度な負荷集中を避けることができます。均等に負荷が分散されることで、システム全体の安定性が向上し、処理の遅延やシステムダウンのリスクを軽減できます。
さらに、システム全体の性能向上にも貢献します。非対称型多重処理方式では、それぞれの処理装置に特化した設計を施すことができます。例えば、全体の管理を行う主処理装置は、管理業務に適した設計にすることができます。また、特定の計算処理を行う従処理装置は、その計算処理に特化した設計にすることができます。このように、処理装置ごとに最適な設計を行うことで、それぞれの処理装置の性能を最大限に引き出し、システム全体の性能向上に繋げることができます。これは、全ての処理装置が同じ役割を持つ対称型多重処理方式では実現できない利点です。
このように、非対称型多重処理方式は、単純な構造、安定性の向上、性能の向上といった様々な利点を持ち、システムの効率的な運用に大きく貢献します。役割分担を明確にすることで、それぞれの処理装置の能力を最大限に活かすことができるため、様々な場面で有効な方式と言えるでしょう。
| 非対称型多重処理方式の利点 | 説明 |
|---|---|
| システム構造の単純化 | 処理装置ごとに役割が明確に割り当てられているため、システム設計・実現が容易になり、開発期間の短縮や開発費用の削減につながる。 |
| システム全体の安定性向上 | 役割ごとに処理装置が割り当てられているため、特定の処理装置への過度な負荷集中を避け、システム全体の安定性が向上し、処理の遅延やシステムダウンのリスクを軽減できる。 |
| システム全体の性能向上 | 処理装置ごとに特化した設計を施すことができるため、それぞれの処理装置の性能を最大限に引き出し、システム全体の性能向上につながる。 |
欠点

非対称型多重処理方式には、いくつかの難点があります。まず、主処理装置への依存度が高いことが挙げられます。この方式では、主処理装置が全体の指揮を執り、他の処理装置に仕事を割り振ります。そのため、もし主処理装置に不具合が生じると、全体の制御が失われ、システム全体が停止してしまう恐れがあります。これは、まるで司令塔が機能しなくなったために、全体の連携が崩れてしまうようなものです。
次に、処理装置間での情報のやり取りに時間がかかることも問題です。それぞれの処理装置が別々に作業を行うため、作業に必要な情報を共有するためには、処理装置間で情報の送受信が必要になります。この情報のやり取りにはどうしても時間がかかり、処理全体の遅延につながる可能性があります。特に、処理装置間で大量の情報をやり取りする必要がある場合は、この遅延の影響が大きくなり、システム全体の性能を低下させる可能性があります。これは、複数の担当者で作業を分担している際に、担当者間の連絡に時間がかかって全体の作業効率が落ちてしまうのと似ています。
さらに、補助処理装置の性能がシステム全体の性能に大きな影響を与えることも欠点の一つです。主処理装置が指示を出し、補助処理装置が実際に作業を行うため、補助処理装置の処理能力が低いと、全体の処理速度が遅くなってしまいます。これは、指示を出す人は優秀でも、実際に作業を行う人の能力が低いと、全体の成果が上がらないのと同じです。そのため、補助処理装置を選ぶ際には、システム全体の性能を考慮して、適切な性能を持つ装置を選ぶ必要があります。
このように、非対称型多重処理方式は、主処理装置への依存や処理装置間の通信による遅延、補助処理装置の性能への影響など、いくつかの課題を抱えています。これらの欠点を理解した上で、適切な対策を講じる必要があります。
| 難点 | 説明 | 例え |
|---|---|---|
| 主処理装置への依存度が高い | 主処理装置が全体の指揮を執るため、主処理装置に不具合が生じるとシステム全体が停止する恐れがある。 | 司令塔が機能しなくなると全体の連携が崩れる。 |
| 処理装置間での情報のやり取りに時間がかかる | 処理装置間で情報の送受信が必要なため、処理全体の遅延につながる可能性がある。 | 複数の担当者で作業を分担している際に、担当者間の連絡に時間がかかって全体の作業効率が落ちる。 |
| 補助処理装置の性能がシステム全体の性能に大きな影響を与える | 補助処理装置の処理能力が低いと、全体の処理速度が遅くなる。 | 指示を出す人は優秀でも、実際に作業を行う人の能力が低いと、全体の成果が上がらない。 |
対称型との違い
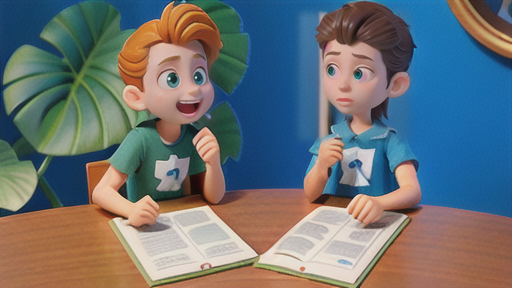
同じ種類の部品を複数組み合わせることで処理能力を高める仕組みを、多重処理といいます。この多重処理には、大きく分けて対称型と非対称型の二つの方式があります。両者の違いを、役割分担、処理の柔軟性、制御の複雑さの観点から見ていきましょう。
まず、対称型では、全ての処理装置は平等な役割を担います。どの装置も、他の装置と同じように、あらゆる処理を実行できます。例えるなら、全員が同じ技能を持つ職人集団のようなものです。全員がどの作業もこなせるため、誰かが休んでも他の人が代わりを務められます。これが処理の柔軟性に繋がります。しかし、全員が同じように働くため、全体の作業手順を細かく指示する必要があり、制御が複雑になります。
一方、非対称型では、処理装置ごとに役割が固定されています。親分役の「主処理装置」と、子分役の「従処理装置」による階層構造になっています。例えるなら、監督と作業員のような関係です。監督は指示を出し、作業員は指示に従って作業を行います。役割が決まっているため制御は単純になりますが、特定の作業しかできない作業員しかいない場合、その作業に問題が発生すると全体の作業が滞ってしまいます。このように、非対称型は柔軟性が低いという欠点があります。
どちらの方式にも利点と欠点があるため、状況に応じて適切な方式を選ぶ必要があります。例えば、刻々と変化する状況への対応が求められるシステムでは、単純な制御で確実に処理を進められる非対称型が適していることがあります。反対に、様々な処理に対応できる汎用性の高いシステムでは、柔軟性が高い対称型が適していることがあります。システムの目的や求められる性能を考慮し、最適な方式を選ぶことが大切です。
| 項目 | 対称型 | 非対称型 |
|---|---|---|
| 役割分担 | 全ての処理装置が平等な役割 | 処理装置ごとに役割が固定(主処理装置と従処理装置) |
| 処理の柔軟性 | 高(誰が休んでも代替可能) | 低(特定の装置に障害が発生すると全体の作業が滞る) |
| 制御の複雑さ | 複雑(全体の作業手順を細かく指示する必要がある) | 単純(役割が決まっているため) |
| 例え | 全員が同じ技能を持つ職人集団 | 監督と作業員 |
まとめ

複数の処理装置を用いて同時に作業を行う仕組みを、処理の進め方によって大きく二つに分けることができます。一つは処理装置全てが対等な立場で働く対称型、もう一つは親分と子分のように役割分担を決めて働く非対称型です。今回のまとめでは、この非対称型について詳しく見ていきます。
非対称型の特徴は、親分役の処理装置、つまり主となる処理装置と、子分役の処理装置、つまり従となる処理装置が明確に役割分担されている点です。この仕組みにより、全体の指示を出す親分役と、実際に作業を行う子分役を分けることで、作業の流れが単純になります。例えば、親分が全体の指示を出し、子分たちがそれぞれの担当作業に集中することで、全体を管理する手間が省け、作業をスムーズに進めることができるのです。また、特定の子分にだけ作業が集中するのを防ぎ、処理装置全体の負担を均一にすることも可能です。
しかし、非対称型にも弱点があります。親分役の処理装置に不具合が生じると、子分役への指示が出せなくなり、システム全体が停止してしまう可能性があるのです。これは、親分役がシステム全体の制御を担っているため、親分役の動作が止まってしまうと、子分役も作業を続けられなくなってしまうからです。例えるならば、オーケストラの指揮者が倒れてしまうと、演奏者たちは指揮者の指示なしに演奏を続けることができず、演奏が中断されてしまうようなものです。
システム構築において、処理装置を複数用いる際は、対称型と非対称型のどちらが良いか、それぞれの長所と短所を比較検討することが重要です。非対称型は、役割分担が明確で管理しやすい反面、主となる処理装置への依存度が高く、その装置に問題が生じるとシステム全体が影響を受けるというリスクがあります。システムの特性や求める性能、安定性を考慮し、適切な方式を選ぶことで、システム全体の効率と安定性を最大限に高めることができます。
| 項目 | 非対称型マルチプロセッシング |
|---|---|
| 特徴 | 親分役(主)と子分役(従)の処理装置が明確に役割分担されている。 |
| メリット |
|
| デメリット | 親分役の処理装置に不具合が生じると、システム全体が停止する可能性がある。 |
| システム構築時の注意点 | 対称型と非対称型のどちらが良いか、それぞれの長所と短所を比較検討する必要がある。非対称型は管理しやすい反面、主となる処理装置への依存度が高く、その装置に問題が生じるとシステム全体が影響を受けるリスクがある。 |
