電源を切っても大丈夫!フラッシュメモリの利点

ITを学びたい
先生、『flash memory』(フラッシュメモリー)って電源を切ってもデータが消えないんですよね? どういう仕組みなんですか?

IT専門家
そうだね、電源を切ってもデータが消えないよ。 電気を使わずに情報を記憶する仕組みで、電気を流すと記憶内容を書き換えることもできるんだ。 例えるなら、黒板にチョークで文字を書いて、消しゴムで消せるようなものだね。

ITを学びたい
なるほど! 普通のメモリーは電源を切ると消えるのに、フラッシュメモリーは消えないのは不思議ですね。 黒板にチョークで書いた文字のように、電源を切っても記憶が残るんですね!

IT専門家
その通り! この特徴のおかげで、パソコンのUSBメモリーや携帯電話、デジカメなど、色々なところで使われているんだよ。
flash memoryとは。
コンピューター関係の言葉で『フラッシュメモリー』というものがあります。これは、半導体を使った記憶装置の一種です。電気を切っても記憶した内容が消えない、ロムと呼ばれる記憶装置と、記憶した内容を書き換えることができる、ラムと呼ばれる記憶装置の両方の特徴を持っています。この記憶装置をカードのような形にしたものがメモリーカードで、デジタルカメラやデジタル音楽プレーヤー、携帯電話などで広く使われています。フラッシュメモリーは、フラッシュロムやフラッシュイーイーピーロムとも呼ばれます。
消えない記憶装置

電気を供給しなくても情報を記憶し続けることができる記憶装置のことを、不揮発性記憶装置と言います。この種類の記憶装置の一つに、皆さんがよく知っているものがあります。それは、ハードディスクです。情報を記録するパソコンなどで使われていますね。ハードディスクと同じように、電気がなくても記憶した情報を忘れない記憶装置として、フラッシュメモリというものがあります。
フラッシュメモリは、ハードディスクに比べてとても小さいです。軽くて薄いため、持ち運びに便利な機器の中に組み込むことができます。例えば、スマートフォンや携帯音楽機器などです。これらの機器は、電源を切っても、保存した写真や音楽などの情報が消えることはありません。これは、フラッシュメモリのおかげです。
フラッシュメモリを使うと、機器の電源を切るたびにデータを別の場所に保存し直す手間が省けます。以前は、フロッピーディスクという記憶装置によく使われていましたが、フロッピーディスクは情報を記録する容量が少なく、取り扱いにも注意が必要でした。しかし、フラッシュメモリは大容量で取り扱いも簡単です。最近では、携帯用のゲーム機器や、持ち運びできる情報記憶装置などにも使われるようになってきました。
フラッシュメモリは、小型で、軽くて、大容量で、取り扱いが簡単という多くの利点を持っています。このため、今後も様々な機器で活用されていくと考えられています。例えば、より多くの情報を記録できるようになり、読み書きの速度もますます速くなっていくでしょう。これからも、フラッシュメモリの進化に注目していく必要があるでしょう。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 不揮発性記憶装置 | 電気を供給しなくても情報を記憶し続けることができる記憶装置 |
| ハードディスク | 不揮発性記憶装置の一種。パソコンなどで情報を記録するために使われる。 |
| フラッシュメモリ | ハードディスクと同じく不揮発性記憶装置。ハードディスクに比べて小型軽量。スマートフォンや携帯音楽機器などに使われる。 |
| フラッシュメモリの利点 | 小型、軽量、大容量、取り扱い簡単 |
| フラッシュメモリの将来 | 更なる大容量化、読み書き速度の高速化 |
| フロッピーディスク(比較対象) | 以前使われていた記憶装置。容量が少なく、取り扱いに注意が必要だった。 |
書き換え可能で便利

電気を消しても記録を残せる便利な記憶装置をご存じですか?その一つに、よく耳にする『フラッシュメモリ』というものがあります。この記憶装置は、パソコンで使う『ハードディスク』のように、何度も情報の書き換えができます。一度書き込んだ情報を消して、新しい情報を書き込むことができるのです。
この『書き換えできる』という特徴は、様々な機械にとって大変重要です。例えば、今や誰もが使う携帯電話。この携帯電話でアプリを新しくしたり、古くなったアプリを消したりするときにも、フラッシュメモリが活躍しています。また、写真を撮るためのカメラでも、撮った写真を追加したり、不要な写真を消したりするときにも、この記憶装置が役立っています。
他にも、持ち運びできる音楽を聴く機械や、テレビ番組を録画する機械など、色々な機器でこのフラッシュメモリが使われています。これらの機器は、常に新しい情報を追加したり、古い情報を更新したりする必要があるので、『書き換えできる』という機能が欠かせないのです。
もし、書き換えができなかったら、情報を書き込んだ後に変更することができず、その度に新しい記憶装置を買わなければなりません。しかし、フラッシュメモリは何度も書き換えられるので、何度も新しい記憶装置を買う必要がなく、費用も抑えられ、環境にも優しいと言えるでしょう。まさに、現代の生活になくてはならない、便利な記憶装置と言えるでしょう。
| 特徴 | 利点 | 使用例 |
|---|---|---|
| 電気を消しても記録を残せる | 何度も情報の書き換えができる | パソコン |
| 書き換え可能 | 様々な機械にとって重要 | 携帯電話 (アプリの追加/削除) |
| カメラ (写真の追加/削除) | ||
| 音楽プレーヤー | ||
| 録画機器 | ||
| 何度も書き換え可能 | 費用を抑えられ、環境にも優しい |
様々な種類と用途
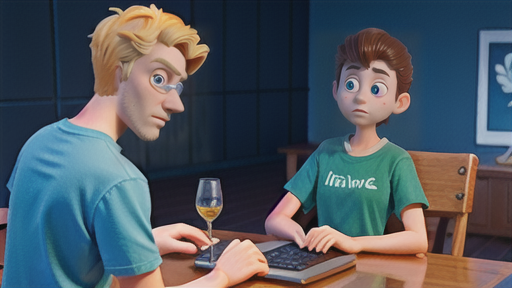
一口に記憶装置といっても、様々な種類があります。中でも、電気を消しても情報を忘れずに持っておける記憶装置を不揮発性記憶装置と呼びます。この不揮発性記憶装置の一種であるフラッシュメモリは、小型で軽く、書き換え可能という特徴から、様々な機器で使われています。
フラッシュメモリには大きく分けて二つの種類があります。一つは読み書きの速度が速いNOR型です。NOR型は少量のデータを読み書きするのに優れており、機器の立ち上げに必要な基本プログラムの記憶領域として使われています。例えば、家電製品や携帯電話、ゲーム機などに組み込まれており、電源を入れた瞬間に機器が動き出すのは、このNOR型フラッシュメモリのおかげです。
もう一つは大容量化に適したNAND型です。NAND型はNOR型に比べて記憶容量が大きく、大量のデータを保存するのに向いています。そのため、写真や動画、音楽などを保存する記憶媒体として広く使われています。身近な例では、携帯電話やデジタルカメラの記録媒体、パソコンの記憶装置などです。最近では、高速な処理速度が必要な高性能計算機にも使われ始めており、今後ますます活躍の場が広がることが期待されます。
このように、フラッシュメモリは種類によって得意とする分野が異なり、それぞれの特性に合わせて様々な機器に組み込まれています。家電製品から自動車、産業機器、医療機器まで、現代社会を支える重要な部品として、なくてはならない存在となっています。
| 種類 | 特徴 | 用途 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| NOR型 | 読み書き速度が速い、少量データ向け | 基本プログラムの記憶領域 | 家電製品、携帯電話、ゲーム機 |
| NAND型 | 大容量化に適している、大量データ向け | 記憶媒体 | 携帯電話、デジタルカメラの記録媒体、パソコンの記憶装置、高性能計算機 |
小型で軽量

薄くて軽く、小さな記憶装置は、近年の技術革新の賜物と言えるでしょう。この小さな装置は、書類入れや筆箱に入るほど小さく、重さもほとんど感じません。切手ほどの大きさで、薄い板のような形をしたものから、親指ほどの大きさの棒状のものまで、様々な形があります。
特に、写真や動画を保存するための小さなカードや、情報を持ち運ぶための小さな棒は、手軽に持ち運べるため、大変便利です。例えば、旅先で撮った写真や動画をすぐに保存したり、会議で使う資料を持ち運んだり、といった用途に最適です。また、音楽を入れて持ち運ぶこともできます。
この小さな記憶装置は、携帯電話や写真機のような、小型化が求められる機器に搭載する記憶装置としてまさにうってつけです。なぜなら、機器全体の大きさと重さを抑えるのに役立つからです。また、小さな部品なので、機器内部の限られた空間を有効活用できます。機器の設計者は、この小さな記憶装置のおかげで、部品の配置や機器の形を自由に設計できるようになりました。
このように、薄くて軽く、小さな記憶装置は、持ち運びやすさと機器設計の自由度という二つの利点を持っています。この二つの利点は、常に持ち歩く情報機器の発展に大きく貢献してきたと言えるでしょう。今後も、さらに小型化・軽量化が進むことで、私たちの生活はますます便利になっていくでしょう。
| 特徴 | メリット | 用途例 |
|---|---|---|
| 薄くて軽い 小さい(書類入れ、筆箱に入る、切手大~親指大) |
手軽に持ち運べる | 旅先での写真・動画保存 会議資料の持ち運び 音楽の持ち運び |
| 小型化が求められる機器に搭載可能 | 機器全体の大きさと重さを抑える 限られた空間を有効活用 部品の配置や機器の形を自由に設計できる |
携帯電話、写真機等 |
| 持ち運びやすさ 機器設計の自由度 |
常に持ち歩く情報機器の発展に貢献 |
衝撃に強い

衝撃に強いことは、フラッシュメモリの大きな利点の一つです。この特徴は、構造的な違いから生まれています。よく比較される記憶装置である磁気記憶装置は、情報を記録するために円盤を回転させ、磁気ヘッドと呼ばれる部品を動かしてデータを読み書きします。このため、磁気記憶装置は、物理的な衝撃を受けると、回転する円盤や磁気ヘッドが損傷し、データが壊れてしまうことがあります。例えば、機器を落としたり、強い振動を与えたりすると、データの読み書きができなくなるといった深刻な問題が発生する可能性があります。
一方、フラッシュメモリは、電子の流れを利用して情報を記録するため、磁気記憶装置のような物理的な可動部分がありません。この構造上の違いが、衝撃に対する強さに繋がっています。つまり、フラッシュメモリは、落としたり、振動を与えたりしても、磁気記憶装置のように物理的な損傷を受けにくいため、データが壊れる心配が少なくて済みます。
このため、フラッシュメモリは、持ち運ぶことが多い機器や、振動の多い環境で使用される機器に最適です。例えば、常に持ち歩く携帯型の音楽再生機や、車の走行中の振動に晒される映像記録機など、衝撃によるデータ破損のリスクが高い機器には、フラッシュメモリが採用されています。また、近年では、小型で軽量という特徴も活かして、様々な機器に広く使われています。磁気記憶装置に比べて高価であるという欠点もありますが、衝撃に強いという利点は、多くの場面で大きなメリットとなっています。
| 項目 | 磁気記憶装置 | フラッシュメモリ |
|---|---|---|
| 記録方式 | 円盤の回転と磁気ヘッドの動き | 電子の流れ |
| 可動部分 | あり(円盤、磁気ヘッド) | なし |
| 衝撃への強さ | 弱い | 強い |
| 衝撃による影響 | 円盤や磁気ヘッドの損傷、データ破損 | データ破損の可能性が低い |
| 用途 | – | 携帯型音楽再生機、車載映像記録機など |
| 価格 | – | 高価 |
低消費電力

電気をあまり使わないことも、この記憶装置の利点です。よく使われる記憶装置である磁気記憶装置と比べると、情報の読み書きや何もしていない時の電気の使い方がずっと少なくなっています。これは、電池で動く機械にとって、とても大切なことです。
携帯電話や板状の携帯情報端末などは、電池がどれくらい長く持つのかが重要です。このような機器でこの記憶装置が多く使われているのは、電気をあまり使わないという特徴があるからです。
例えば、動画を見る時を考えてみましょう。磁気記憶装置を使うと、回転する円盤から情報を読み込むため、多くの電気が必要です。一方、この記憶装置は電気的な仕組みで情報を出し入れするため、電気の消費が抑えられます。同じように、音楽を聴く時や写真を撮る時も、電池の持ちに違いが出てきます。
また、記憶装置に情報を書き込む際にも差があります。磁気記憶装置は、情報を書き込むために磁気を変化させる必要があり、これも電気を消費します。この記憶装置は、より少ない電力で情報を書き込むことができます。
さらに、何もしていない待機状態でも、磁気記憶装置は回転を続けるため電気を消費し続けますが、この記憶装置は待機時の消費電力が非常に少ないです。
このように電気をあまり使わないということは、エネルギーの節約にもなります。地球環境にも優しい技術と言えるでしょう。
| 項目 | フラッシュメモリ | 磁気記憶装置 |
|---|---|---|
| 消費電力 | 少ない | 多い |
| 読み書き速度 | 速い | 遅い |
| 待機電力 | 非常に少ない | 多い(回転し続けるため) |
| 用途例 | 携帯電話、タブレット等 | PC等 |
| メリット | 省電力、高速 | 大容量、安価 |
