情報活用格差:デジタルデバイドを考える

ITを学びたい
先生、「デジタルデバイド」って言葉の意味がよくわからないのですが、教えていただけますか?

IT専門家
いいよ。「デジタルデバイド」とは、コンピューターやインターネットを使える人と使えない人の間に生まれる差のことだよ。例えば、インターネットで買い物や色々な手続きができる人と、それができない人の間に生まれる不便さや、仕事を見つけるのが難しいといった格差が生じるんだ。

ITを学びたい
なるほど。つまり、コンピューターやインターネットが使えるかどうかで、生活に差が出てくるということですね。でも、今は誰でもスマホとか持っているから、あまり関係ないんじゃないですか?

IT専門家
確かにスマホを持っている人は多いけど、使い方には差があるんだよ。例えば、インターネットで情報を探すのが得意な人と苦手な人がいるよね。それに、地域によってはインターネット回線が遅くて使えない場所もある。そういった様々な要因で「デジタルデバイド」は今でも問題になっているんだ。
digital divideとは。
情報技術、特にコンピューターやインターネットを使いこなせる人とそうでない人の間には、様々な格差が生じています。この格差は、就職の機会や収入の差といった個人的なものから、地域や国同士の差といった大きなものまで、様々なレベルで見られます。この格差のことを『デジタルデバイド』、または『情報格差』と言います。
情報活用格差とは

情報活用格差、いわゆる電子情報による隔たりとは、計算機や情報網といった情報伝達技術を使いこなせる人とそうでない人の間に生じる様々な差のことを指します。この差は、単に技術の利用能力の差にとどまらず、仕事を得る機会、稼ぎ、学び、医療、社会への参加など、暮らしの様々な側面に影響を与えます。
情報伝達技術を使いこなせる人は、より良い仕事に就きやすく、稼ぎも増えやすい傾向があります。例えば、情報網を使って最新の求人情報を探したり、自分の技能を売り込んだりすることで、より有利な条件で仕事を見つけることができます。また、会社でも、情報伝達技術を使いこなせることで、業務効率を上げたり、新しい事業を立ち上げたりするなど、活躍の場が広がります。その結果、収入の増加にもつながりやすいと言えるでしょう。
さらに、最新の医療情報や教育内容にも容易に触れることができ、自ら学ぶことや健康管理にも役立てることができます。例えば、健康に関する疑問をすぐに調べたり、専門家の意見を聞いたりすることで、病気の予防や早期発見に役立てられます。また、オンライン講座などを通じて、いつでもどこでも好きな時間に学ぶことができ、自己啓発にもつながります。
一方、情報伝達技術を使いこなせない人は、これらの恩恵を受けることが難しく、社会的に不利な立場に置かれがちです。仕事の情報を得にくかったり、応募書類の作成に苦労したりすることで、仕事を得る機会が制限される可能性があります。また、医療情報や教育内容にも触れにくいため、健康管理や自己啓発の機会も失われがちです。
この差は、個人間だけでなく、地域間や国同士の間にも存在し、社会全体の不平等を広げる要因となっています。都市部と地方では、情報網の整備状況に差があることが多く、地方に住む人は情報へのアクセスが制限される場合があります。また、国同士の間でも、情報伝達技術の普及度に大きな差があり、発展途上国では情報活用格差が深刻な問題となっています。現代社会において、情報伝達技術は社会生活を送る上で欠かせない基盤となっています。そのため、情報活用格差をなくすことは、全ての人にとって公平で公正な社会を実現するために欠かせない課題と言えるでしょう。
| 情報活用格差の影響 | 情報伝達技術を使いこなせる人 | 情報伝達技術を使いこなせない人 |
|---|---|---|
| 仕事 | 良い仕事に就きやすい、稼ぎやすい、業務効率向上、新規事業の立ち上げ | 仕事の情報を得にくい、応募書類作成に苦労する、仕事を得る機会が制限される |
| 学び/健康 | 最新の医療情報・教育内容に容易にアクセス、自己学習、健康管理 | 医療情報・教育内容に触れにくい、健康管理・自己啓発の機会が少ない |
| 社会への影響 | – | 個人間、地域間、国家間の格差拡大 |
情報活用格差の種類

情報を取り扱う能力の差は、大きく分けて三つの種類に分けることができます。
一つ目は、機器や通信回線を使う機会の差です。同じ国の中でも、都会と地方では、使える通信回線の速さや料金に大きな違いがある場合があります。地方では回線の整備が遅れている地域もあり、高速なインターネットを利用できない、または利用料金が高額になることがあります。また、経済的な理由でパソコンや携帯電話などの機器を買えない人もいます。このような機器や回線へのアクセスの差は、情報活用格差を大きく広げる要因の一つです。
二つ目は、情報を使いこなす能力の差です。パソコンやインターネットをうまく使うためには、ある程度の知識や技術が必要です。どのような情報を探したいか、どのように検索すればよいか、情報の信頼性をどのように判断するかなど、様々な能力が求められます。教育レベルや年齢、これまでの経験によって、これらの能力に差が生じる場合があります。特に、高齢者や障害のある方など、情報通信技術の利用に苦労する方々もいます。周りの人が使い方を教えたり、使いやすい機器やサービスを提供したりするなど、支援が必要です。
三つ目は、情報を使う目的の差です。情報通信技術は、娯楽のためだけでなく、仕事や教育、医療など、様々な目的で使われます。例えば、仕事で使う人は最新の技術情報をいち早く入手し、仕事の効率を上げるために活用します。また、教育の場では、子供たちがインターネットを使って様々な情報を調べ、学習に役立てています。医療の現場では、医師が患者の症状や検査結果をインターネットで確認し、より正確な診断を行うために活用しています。このように、情報を使う目的によって、得られる情報の種類や質、そしてその効果に差が生じる可能性があります。
これら三つの種類の格差が複雑に絡み合い、情報活用格差全体の大きな問題となっています。情報へのアクセス機会の差をなくし、誰もが情報技術を使いこなせるように教育や支援を行い、様々な目的で情報が活用できる環境を整備することが重要です。

情報活用格差が及ぼす影響

情報を得たり使ったりする能力の差が、社会全体に様々な悪い影響を与えていることは明らかです。教育の場を考えてみましょう。今では、多くの学校で電子機器を使った学習が行われています。しかし、家庭に電子機器やインターネット回線がない子どもたちは、授業についていくことが難しく、他の子供たちと同じように学ぶ機会を失ってしまいます。これは、子どもたちの将来の可能性を狭めてしまう大きな問題です。
医療の面でも同様の問題が生じています。最新の医療情報や、病院の予約システムなどは、ほとんどがインターネット上で提供されています。情報機器を使えない人は、必要な情報を得ることができず、適切な治療の機会を逃してしまうかもしれません。また、遠隔医療の普及により、地方に住む人でも都市部の専門医の診察を受けられるようになりましたが、情報機器がないためにこの恩恵を受けられない人もいます。
経済活動においても、情報機器の活用は不可欠です。インターネットを使えば、世界中の人と商品やサービスを売買できます。しかし、情報機器を使えない人は、このような機会に参加することが難しく、収入を得るチャンスを逃してしまいます。さらに、行政手続きもインターネット上で行われることが増えています。情報機器を使えない人は、必要な手続きができず、様々な行政サービスを受けられない可能性があります。
このように、情報機器を使える人と使えない人の間には、大きな格差が生じています。この格差は、教育、医療、経済活動、行政サービスなど、社会のあらゆる分野に影響を及ぼし、人々の生活に深刻な不平等をもたらしています。この問題を解決するためには、情報機器やインターネット回線へのアクセスを改善するだけでなく、誰もが情報機器を使いこなせるようにするための教育や支援が必要です。そうでなければ、情報活用格差はさらに拡大し、社会の分断を深めることになるでしょう。
| 分野 | 情報機器が使える人のメリット | 情報機器が使えない人のデメリット |
|---|---|---|
| 教育 | 電子機器を使った学習機会 | 授業についていくのが難しい、学習機会の喪失 |
| 医療 | 最新の医療情報入手、オンライン予約、遠隔医療 | 必要な情報入手困難、適切な治療機会の喪失、遠隔医療の恩恵を受けられない |
| 経済活動 | 世界中との商取引、収入機会 | 商取引機会への参加困難、収入機会の喪失 |
| 行政サービス | オンライン手続き | 必要な手続き不可、行政サービスを受けられない可能性 |
情報活用格差の解消に向けた取り組み
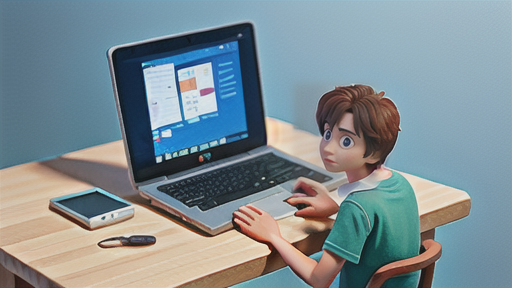
近頃、情報通信技術の進歩は目覚ましく、暮らしを便利で豊かにする様々な機会を提供しています。しかし、同時に情報通信技術を使いこなせる人とそうでない人の間に格差が生じているのも事実です。この情報活用格差は、社会全体にとって大きな課題であり、解消に向けて多方面からの取り組みが不可欠です。
まず、政府は情報通信技術の基盤となる設備の整備を進める必要があります。地方でも都市部と同じように高速で安定した通信環境が使えるように整備を進め、すべての人が等しく情報通信技術を利用できる環境を構築することが重要です。さらに、情報通信技術を使いこなすための教育支援も必要です。学校教育の場では、子供たちが幼い頃からコンピュータやインターネットに慣れ親しみ、正しい知識と技能を身につけるよう指導する必要があります。大人に対しても、地域社会で学習機会を提供することで、情報通信技術を活用できる人を増やす必要があります。
企業もまた、情報活用格差の解消に大きな役割を担っています。新しい技術を使った商品やサービスを作る際には、誰でも簡単に使えるように設計することが大切です。例えば、文字の大きさや色の変更、音声読み上げ機能などを取り入れることで、高齢者や障害のある人でも容易に利用できるようになります。また、地域社会では、情報通信技術の利用に困っている人を支える仕組み作りが重要です。例えば、地域センターなどで無料の講習会を開いたり、ボランティアが個別に指導したりすることで、情報通信技術の恩恵を誰もが受けられるように支援していく必要があります。高齢者や障害のある人など、特に支援が必要な人々に対しては、き寄り細やかな支援体制を構築することが大切です。
そして、私たち一人ひとりも、情報通信技術に関する知識や技能を積極的に学ぶ姿勢が重要です。新しい技術を学ぶことに臆ることなく、積極的に情報に触れ、その変化に適応していく努力が必要です。情報活用格差の解消は容易ではありませんが、政府、企業、地域社会、そして個人がそれぞれの役割を果たし、協力して取り組むことで、すべての人が情報通信技術の恩恵を享受できる、より良い社会を築くことができるはずです。
| 主体 | 役割 |
|---|---|
| 政府 |
|
| 企業 |
|
| 地域社会 |
|
| 個人 |
|
私たちができること

情報技術の活用方法が人によって大きく異なることで生じる格差、いわゆる情報活用格差をなくすために、私たち一人一人にできることがあります。まず情報活用格差の問題に関心を持つことが大切です。新聞やテレビ、インターネットなど様々な媒体で情報活用格差について知り、現状を正しく理解するようにしましょう。
理解を深めたら、周りの家族や友人、職場の同僚などに情報活用格差の問題について話してみましょう。周りの人々にこの問題を伝えることで、社会全体の意識を高めることにつながります。情報を共有し、共に考えることで、より良い解決策が見えてくるかもしれません。
また、地域社会で活動することも効果的です。例えば、パソコンや携帯電話などの機器の扱いに慣れていない高齢者や障害のある方々を支援するボランティア活動に参加してみましょう。地域の人々に寄り添い、技術的なサポートをすることで、地域社会における情報活用格差の縮小に貢献できます。
家庭では、子供たちに情報通信機器の正しい使い方を教えることが重要です。インターネットの危険性や個人情報の保護など、安全に機器を使うための知識を教え、情報機器を適切に活用する能力を育みましょう。子供たちが将来情報活用格差に直面しないように、家庭での教育が重要です。
そして、私たち自身も情報技術に関する新しい知識や技能を学び続ける努力を怠らないようにしましょう。技術は常に進化しています。常に学び続けることで、自らの情報活用能力を高め、情報社会の変化に対応できる力を身につけることができます。これらの行動は、一見小さな取り組みかもしれませんが、一人一人の行動が積み重なることで、大きな力となり、情報活用格差のない、すべての人が技術の恩恵を受けられる社会の実現につながるのです。

