隠れた宣伝:ステマとは何か?

ITを学びたい
先生、「こっそり宣伝」っていう言葉の意味がよくわからないんですけど、普通の宣伝と何が違うんですか?

IT専門家
良い質問だね。普通の宣伝は、広告だとすぐにわかるよね? テレビCMや電車の広告みたいに。でも「こっそり宣伝」は、宣伝だと気づかれないように工夫されているんだ。例えば、友達がすごく良い物を教えてくれたとしよう。でも実は、その友達は会社からお金をもらって、良いふりをしていたとしたらどうだろう? これが「こっそり宣伝」なんだよ。

ITを学びたい
なるほど! 友達のふりをして宣伝するってことですね。でも、それってバレないんですか?

IT専門家
バレにくいように工夫されているんだけど、最近はインターネットなどで情報が広がりやすいから、バレることもあるね。バレてしまうと、会社の評判が悪くなってしまうこともあるから、こっそり宣伝は倫理的に問題があると言われているんだよ。
stealth marketingとは。
情報技術に関連した言葉で、『ステルスマーケティング』というものがあります。これは、会社の商品やサービスの宣伝を、お客さんに宣伝だと気づかれないように行うことです。いわゆる『さくら』を使った宣伝方法で、関係者がインターネットなどで普通のお客さんのふりをして、その商品やサービスを褒めたり、勧めたりします。略して『ステマ』とも言います。他にも『アンダーカバーマーケティング』という言い方もあります。『ステルス』は、こっそり行うという意味です。
隠れた宣伝の正体
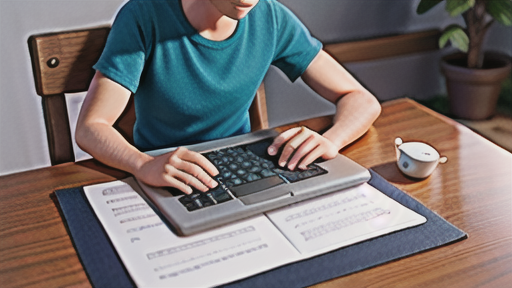
こっそりと行われる宣伝、いわゆる「やらせの口コミ」は、お客さんに宣伝だと気づかれないように商品やサービスを売り込む方法です。まるで普通に商品を買った人かのように装って、口コミのサイトや人のつながりの場で良い評価を書いたり、商品を勧める文章を書いたりします。一見すると、本当に使った人の感想のように見えるため、宣伝だと気づかずに情報を受け取るお客さんが多く、その影響力は無視できません。
企業にとっては、テレビや雑誌などの広告よりも本物の感想のように見えるため、効果的な宣伝方法として使われることがあります。たとえば、人気の料理人が、ある調味料を「愛用している」とブログに書けば、その調味料が急に売れ始める、といった具合です。また、たくさんの人に商品を使ってもらい、良い口コミを広げてもらうことで、まるで流行のように仕立て上げることも可能です。
しかし、お客さんをだます行為であり、道徳的に問題視されています。お客さんは、本当に良い商品だと信じて買ってしまうため、後から騙されたと感じる人も少なくありません。本来、口コミは、実際に商品やサービスを使った人の正直な感想が書かれる場であるべきです。やらせの口コミは、このような健全な情報交換の場を壊してしまう可能性があります。
さらに、やらせの口コミが広がると、本当に良い商品を作っている企業が損をすることにもなります。良い商品を作っても、口コミで悪い評価ばかり書かれてしまったら、売れなくなってしまいます。やらせの口コミは、公正な競争を阻害することにもつながりかねません。そのため、お客さんを守るためにも、やらせの口コミを見抜く目を養うことが大切です。怪しいと思ったら、他の人の口コミもよく読んで、商品のことをじっくり調べてから買うように心がけましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | お客さんに宣伝だと気づかれないように商品やサービスを売り込む方法。口コミサイトなどを使って、良い評価を書き込んだり商品を勧める。 |
| 影響力 | 本物の感想に見えるため、気づかずに情報を受け取る人が多く、影響力は無視できない。 |
| 企業側のメリット | テレビCMなどの広告より本物の感想に見えるため効果的。 |
| 例 | インフルエンサーが愛用しているとブログに書けば商品が売れる。 |
| 問題点 | お客さんを騙す行為であり道徳的に問題。健全な情報交換の場を壊す可能性がある。本当に良い商品を作っている企業が損をする。公正な競争を阻害する。 |
| 対策 | やらせの口コミを見抜く目を養う。怪しいと思ったら他の口コミもよく読んで、商品のことをじっくり調べてから買う。 |
ステマの種類と手法

宣伝と見せかけて、消費者に気付かれないように商品やサービスを売り込む行為は、様々な方法で行われています。その種類と方法をいくつかご紹介します。
まず、よく見られるのが、有名人や評判の高い発信者が、まるで自分が好きで使っているかのように商品を紹介する方法です。実際には、企業からお金をもらって宣伝しているにもかかわらず、それを隠して伝えます。そのため、聞いている人たちは、純粋なおすすめだと勘違いしてしまうことがあります。宣伝だと分かっていれば、客観的に判断できますが、隠されていると、つい信じて買ってしまいがちです。
次に、一般の人になりすまして、インターネット上の掲示板や個人の日記などに、商品を褒めちぎる書き込みをする方法があります。まるで本当にその商品を使って、効果に感動したかのように書き込みます。しかし、実際は、企業からお金をもらって書いている、いわゆる「さくら」と呼ばれる人たちです。こうした書き込みは、いかにも一般の人の声のように見えるため、信じてしまう人も少なくありません。
また、ランキングサイトなどで、実際よりも順位を高く表示させる方法もあります。お金を払って上位に表示させ、多くの人に見られるように仕向けます。ランキング上位であれば、良い商品だと勘違いして購入してしまう人もいるでしょう。
さらに、記事風の広告を作成し、普通のニュース記事のように見せかける方法も増えています。一見すると、客観的な情報のように見えますが、実際は企業が宣伝のために作っています。広告だと気付かずに読んでしまい、商品の良さを信じてしまう可能性があります。
このように、宣伝と分からないように商品を売り込むやり方は様々です。消費者は、こうした巧妙な宣伝方法に惑わされないように注意する必要があります。
| ステルスマーケティングの種類 | 手法 |
|---|---|
| インフルエンサーマーケティング | 有名人や評判の高い発信者が、商品提供を受けていることを隠して、あたかも自分が好きで使っているかのように商品を紹介する。 |
| 口コミ偽装 | 一般の人になりすまして、インターネット上に商品を褒めちぎる書き込みをする(さくら)。 |
| ランキング操作 | ランキングサイトなどで、金銭と引き換えに実際よりも順位を高く表示させる。 |
| ネイティブ広告 | 記事風の広告を作成し、普通のニュース記事のように見せかける。 |
ステマの問題点

いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」とは、宣伝であることを隠して商品やサービスを推奨する行為です。これは、消費者を欺き、市場を歪める深刻な問題を孕んでいます。
まず、ステマは消費者の信頼を大きく損ねます。消費者は、それが宣伝だと知らずに商品やサービスを購入します。もし、その商品やサービスが期待はずれだった場合、消費者は裏切られたと感じ、企業や商品に対する不信感を抱くでしょう。この不信感は、一度芽生えると払拭するのは難しく、企業の将来に大きな影を落とす可能性があります。
また、ステマは公正な競争を阻害するという問題もあります。真摯に商品開発やサービス向上に取り組んでいる企業が、ステマによって不当に市場シェアを奪われることは、健全な経済活動を阻害します。まじめに努力を重ねている企業が正当な評価を受けられない社会は、停滞をもたらし、活力を失うでしょう。
さらに、ステマを見抜くことの難しさも大きな問題です。巧みに隠蔽されたステマは、消費者が宣伝だと気付くことなく、購買意欲を高めてしまいます。インターネットや交流サイトの普及により、誰もが情報を発信できるようになった現代において、ステマを見分ける目を養うことは非常に重要です。そのため、消費者は情報を見極める能力を高め、発信元や情報の信頼性を常に確認する必要があります。情報の真偽を見極める目を養うためには、多様な情報源に触れ、様々な視点から物事を考える習慣を身につけることが大切です。
このように、ステマは消費者の信頼を損ない、公正な競争を阻害し、消費者の判断力を鈍らせる深刻な問題です。健全な市場を維持するためには、消費者、企業、そして行政が一体となって、ステマ撲滅に向けた取り組みを進めていく必要があります。
| ステマの問題点 | 詳細 |
|---|---|
| 消費者の信頼を損なう | 消費者は宣伝と知らずに購入し、期待外れの場合、企業への不信感を持つ。 |
| 公正な競争を阻害する | 真摯に努力する企業が不当に市場シェアを奪われ、健全な経済活動を阻害する。 |
| ステマを見抜くことの難しさ | 巧妙なステマは見抜くのが難しく、消費者の判断力を鈍らせる。情報の真偽を見極める目を養うためには、多様な情報源に触れ、様々な視点から物事を考える習慣を身につけることが重要。 |
法規制と自主規制

宣伝を装った口コミ、いわゆるステルスマーケティング(ステマ)は、消費者の公正な判断を歪める深刻な問題です。そのため、法の力によって規制すると同時に、業界全体で自主的にルールを作り、守っていく必要があります。
ステマを取り締まる法律としては、景品表示法と不正競争防止法が挙げられます。景品表示法は、商品やサービスの品質や価格について、実際よりも優れていると誤解させるような表示を禁じています。ステマはこの法律に抵触する可能性が高いのです。また、不正競争防止法は、他社の営業活動を妨害するような不正な行為を取り締まっています。ステマは消費者の信頼を損ない、公正な競争を阻害するため、この法律にも抵触する可能性があります。これらの法律に違反した場合には、罰金や業務停止命令など、厳しい罰則が科せられます。
法規制に加えて、業界団体による自主規制も重要な役割を担っています。広告業界団体は、ステマに関する指針を定め、会員企業が倫理に反した広告活動を行わないよう指導しています。たとえば、広告と個人の発信を明確に区別することや、宣伝であることを明示することなどを求めています。自主規制は、法規制だけではカバーしきれない問題点にも対応できるという利点があり、業界全体の健全な発展に貢献します。
法規制と自主規制の両輪でステマを撲滅しようと努力は続けられていますが、ステマの手口は巧妙化しています。常に変化する状況に合わせて、規制の強化や自主規制の改善が必要不可欠です。消費者を保護し、公正な市場を維持するために、関係者全員が協力して取り組むことが重要です。
| 種類 | 内容 | 違反した場合 |
|---|---|---|
法規制
|
|
罰金、業務停止命令など |
| 自主規制 (業界団体) |
|
– |
消費者の対策

インターネットや口コミサイトなど、様々な所で商品やサービスの情報があふれる中、宣伝と気づかずに広告を見てしまう、いわゆるステルスマーケティング(ステマ)の被害を防ぐには、私たち消費者が情報を見極める目を養うことが大切です。
まず、情報の出どころがどこなのか、信頼できる所なのかを確認しましょう。誰がその情報を発信しているのか、発信者の立場や意図をしっかりと見極めることが重要です。
また、一つの情報源だけでなく、複数の情報源を比較検討することも大切です。色々な場所で情報を集め、内容に違いがないか、偏りがないかを確認することで、より正確な情報を得ることができます。
口コミサイトやSNSの書き込みは、手軽に多くの人の意見を見ることができる便利なツールですが、全てをそのまま信じてはいけません。誰でも自由に書き込めるため、中には事実とは異なる情報や、特定の意図を持った書き込みが紛れている可能性があります。過剰に褒めるだけの書き込みや、不自然な表現、また、似たような書き込みが多数ある場合は、ステマを疑ってみましょう。
商品の公式な情報源、例えば企業の公式な案内や公的機関の発表なども確認することをお勧めします。公式な情報と口コミサイトなどの情報を比較することで、情報の信憑性をより確実に判断することができます。
情報の真偽を見極める力は、私たちの暮らしを守る上で非常に重要です。様々な情報に惑わされず、賢明な判断をするために、日頃から情報を見極める目を養い、信頼できる情報源を確保するようにしましょう。
| ステマ対策のポイント | 具体的な行動 |
|---|---|
| 情報の出どころを確認 | 発信者とその立場・意図を確かめる。信頼できる情報源かを確認する。 |
| 複数の情報源を比較検討 | 様々な場所で情報を集め、内容の差異や偏りを確認する。 |
| 口コミサイトやSNSの書き込みを鵜呑みにしない | 過剰な賞賛、不自然な表現、似た書き込みの多さに注意し、ステマを疑う。 |
| 公式情報を活用 | 企業の公式案内や公的機関の発表を確認し、口コミサイトの情報などと比較する。 |
| 情報を見極める目を養う | 日頃から情報源の信頼性を確認し、情報の真偽を見極める習慣をつける。 |
これからの課題

インターネットの広がりと共に、ステルスマーケティング(ステマ)はより巧妙さを増し、私たちの生活に浸透してきています。巧妙に隠された宣伝行為は見破ることが難しく、消費者を欺き、公正な競争を阻害する大きな問題となっています。この問題に対処するためには、消費者、企業、そして行政が三位一体となって取り組む必要があります。
まず、消費者は情報を読み解く能力を高め、ステマを見抜く目を養うことが重要です。インターネットには多くの情報が溢れていますが、その中には真実でない情報や、意図的に操作された情報も含まれています。情報の出所や発信者の意図を確認する習慣を身につけ、情報に惑わされないように注意する必要があります。口コミサイトや商品の紹介記事を読む際には、発信者が誰なのか、どのような意図で情報を発信しているのかを注意深く見極める必要があります。
企業は、倫理に則った広告活動を実践し、消費者の信頼を獲得する必要があります。消費者を欺くようなステマ行為は、短期的な利益をもたらすかもしれませんが、長期的には企業の信頼を失墜させ、大きな損失につながる可能性があります。透明性が高く、誠実な広告活動を行うことで、消費者の信頼を獲得し、持続的な企業成長を実現することができます。企業は、自社の商品やサービスを正しく理解してもらうために、分かりやすく正確な情報を提供する必要があります。
行政は、法の整備や啓発活動を通じて、ステマの蔓延を防ぐ役割を担っています。ステマ行為を取り締まるための明確なルールを設け、違反した場合には適切な罰則を科す必要があります。また、消費者や企業に対してステマ問題の深刻さを周知し、啓発活動を行うことも重要です。ステマに関する情報を分かりやすく提供することで、消費者と企業の意識を高め、ステマのない健全な市場環境を整備する必要があります。
ステマのない健全な社会を実現するためには、消費者、企業、行政がそれぞれの役割を果たし、社会全体で協力していくことが不可欠です。インターネットという便利な道具を正しく使い、公正な情報に基づいた社会を築いていくために、私たち一人ひとりが意識を高め、行動していく必要があります。

